番外編:日本映画に未来はあるのか?
本ブログではアメリカに関連するテーマを取り上げていますが、今回は「番外編」です。夏休みの最中なので、あまり生真面目なテーマだけでは、読む意欲が削がれるでしょう。今回は雑感です。ですから軽く読み流してください。今、ヴィクター・フランケルの『Man’s Search for Meaning』という本を読んでいます。筆者はユダヤ人の精神科医で、アウシュビッツに収容されていた人物です。精神科医という専門的な立場から、収容所の人々の動きを詳細に記述、分析したものです。その中に「delusion of reprieve」という言葉が出てきます。意味は「処刑の延期」というのですが、要するに処刑される最後の瞬間に自分は救われるという妄想のことです。まるで今の日本の状況を表現しているかのような言葉です。社会的状況、政治的状況、文化的状況はもうどうしようもないほど閉塞感に包まれているのに、自分だけは救われるという妄想に人々は浸っている気がしてなりません。”普通の”国民なら、一大デモでも起こっても不思議ではないのに、そうした”健全な怒り”はどこにも見られません。メディアも選挙をショーにすることで喜んでいるようです。必要なのは、”普通の国家”になる前に”普通の国民”になることのような気がします。
大学時代、あるアメリカ人の友人から言われた言葉が今でもはっきりと耳に残っています。それは「日本人はいつも”仕方がない”と言って、何もしようとはしない」という言葉でした。この「仕方がない」というのは、「なるようにしかならない」ということであって、積極的に自分から状況を切り開く意思がないことを意味するのでしょう。昔、アウシュビッツに収容されたユダヤ人は抵抗らしい抵抗もせずにガス室に送られていきました。まだ若かった頃、「どうせ助からないのなら、なぜ抵抗しなかったのか」と不思議に思っていました。それはフランケルのいう「delusion of reprieve」の心理状況だったのかも知れません。「自分だけは最後の瞬間に助かる」そんな幻想で日々と暮らしていたのかも知れません。しかし、皆、ほぼ確実にガス室に送られたのです。
これも台湾で経験したことですが、ロイター通信の台湾のスタッフと台北を一緒に歩いていました。交通信号が変わる瞬間、私は急いで車道を横切ってしまいました。すると、中年の男性が私に向かって大きな声で何かを言い始めました。多分、道路を横断したことを注意したのでしょう。すると一緒にいた台湾人の記者が、その男性に向かって同様に大きな声で言い返し始めました。私を弁護してくれたのでしょう。二人は路上で言い争いを始めました。原因が私にあるのに、その光景を見ながら妙な感じがしました。そのとき感じたことは、「日本では、こんな風にドライに言い争うことはないだろうな。日本の喧嘩は陰湿だけど、ここの喧嘩は見ていて気分が良いほどすっきりしている」ということでした。さらに驚いたのは、二人が言い争っているときに、一人の初老の男性が割って入り、喧嘩を見事に収めてしまったのです。その采配の見事さに感心しました。周囲の人々も、それを見て喝采していました。繰り返しますが、その時の私の印象は、むしろ爽やかなものでした。妙に陰に篭るのではなく、ちゃんと自己主張しあうというのは良いことですが、どうも日本人はそうした対応の仕方が苦手なようです。
最近の日本人は本気で怒らなくなった、泣かなくなったという印象があります。映画評論家の佐藤忠夫は「昔の日本人は良く泣いた」と、どこかに書いています。昔の映画では男性が号泣する場面はたくさんあったそうです。現在は、怒ったり、泣いたりしない分、日本人は従順になったようです。ただ、決して”大人”になったとは思いませんが・・・。”
これも昔の経験ですが、人の行動を理解する良い例になると思いますので書いておきます。私は大学を卒業して銀行員になりました。銀行の寮で暮らしていたのですが、食堂で料理を作っていた女性が辞め、夫婦者の板前が後任でやってきました。しかし、前の女性が作っていた家庭的な料理と比べると、品はいいけど、どうも量が少なかったりして、肉体労働をして寮に戻ってきた行員の胃袋を満足させるものではありませんでした。そこで寮の代表が銀行の人事部と掛け合って、その夫婦を解雇して、新しい人を入れることになりました。新しい料理人がやってきたのですが、料理の内容は板前さんが作っていたときよりも悪くなりました。それから、寮の誰も料理に文句を言わなくなったのです。努力が良い方向に進むときは人は積極的になるのですが、逆の方向に進むかもしれないとなると、沈黙してしまうものです。人事部は寮生の心と行動を実に良く理解していたのでしょう。
以上に挙げた例は、今の日本人の”精神状況”に良く符号する気がしてしかたありません。「何をやっても仕方ない」「声の大きい奴が勝つんだ」「何かをやれば逆に状況が悪くなるかもしれない」という気持が蔓延しているのかも知れません。だったら、自分だけ良い思いをし、金儲けに邁進することが唯一の美徳になるのも”仕方がないこと”かも知れません。
ウォルフレンというオランダのジャーナリストが「日本にはインテリはいない」と喝破したのが、1990年代の初めです。それから10年以上経っていますが、日本の知的状況はさらに悪くなっているのではないでしょうか。尊敬される知的指導者はいなくなり、相手に耳を貸さない声高な論者ばかりが増えているようです。
横道にそれましたが、標題の「日本の映画の未来」について書きます。最近見た映画をベースに日本映画に関する感想を書いてみます。最近では、仕事以外では映画を見るのが唯一の楽しみになっています。昔から映画は大好きで、息子には大学で映画を専攻(脚本)するように勧めたのは私でした。小さいころからいつも映画館に連れて行っていたので、彼も映画が大好きです。ただ、日本の映画界の状況を見ると、「彼は将来苦労するだろうな」という気持を禁じえません。
主に洋画を見ていますが、最近、何本かの邦画を相次いで観ました。ここでは3本の映画を取り上げてみます。もちろん、3本の映画で日本の映画界の全体状況を把握できるわけではありませんが、それなりのヒットしている映画なので、そう大きく外れることはないでしょう。
その映画とは「ローレライ」「亡国のイージス」「妖怪大戦争」です。まず、最初の印象を言いますと、3本とも非常に失望したということです。まず、現在、上映中の「亡国のイージス」ですが、この映画の狙いは何かまったく分かりません。「娯楽映画」なのか、「アクション映画」なのか、「政治映画」なのか・・・。映画の中ではもっともらしい思想的、政治的な背景を出てくるのですが、それがどこまで本気なのか訝ってしまいます。中井貴一に「日本人よ、これが戦争だ!」と叫ばせても、どこにもリアリティがありません。最近、流行のナショナリズムを鼓舞するにしても、あまりにも稚拙です。同じ原作者の「ローレライ」に至っては、何のためにこの映画を作ったのか(小説は読んでいないのでコメントできません)まったく理解不能です。荒唐無稽なストーリーが悪いというのではありません。荒唐無稽でも、リアリティを感じさせる映画はたくさんあります。しかし、「ローレライ」は、今でも、何のためにこの映画を作ったのか、製作者の意図がまったく分かりません。小説が売れているから、映画にすればヒットするだろうという程度の意識で作ったのではないかと思っています。
娯楽映画なら、「亡国のイージス」と同じような内容の映画があります。それはスティーブン・セガール主演の「沈黙の艦隊」で、二級映画ですが、「亡国のイージス」よりもはるかに面白い。この映画もテロリスト(別に思想性があるわけではないですが)が戦艦を奪取して、ミサイルを使って脅迫し、お金をせしめようとする内容です。主人公がスーパーマンのように活躍する痛快娯楽映画です。「亡国のイージス」と同じような設定で、ジェット戦闘機が爆弾を投下するという設定の映画に「ザ・ロック」があります。ショーン・コネリーとニコラス・ケージが主演した映画で、アクションも一流です。アルカトラズ島の元刑務所を占拠したテロリストと戦う映画です。「亡国のイージス」の艦内での打ち合いなど比較にならないほど、戦闘場面には緊張感と迫力があり、面白い映画です。この映画も、最後の場面でミサイルを積んだジェット戦闘機が飛来してきます。それを阻止するために、数分、数秒を争う緊張した場面があります。「亡国のイージス」も、同様な設定があります。「ザ・ロック」では、ニコラス・ケージが必死にミサイルを発射しないように合図を送ります。「亡国のイージス」も、真田広行が演じる主役が手旗信号で合図をします。しかも、それを人工衛星から撮った画像で分かるとうのは、荒唐無稽を通り越してしまっています。それに、このシーンはまるで「ザ・ロック」から借りてきたようなシーンです。しかし、ニコラス・ケージの迫真ある演技と真田広之の演技を比べると、正直、日本映画に対して絶望的な気持になります。
特写のシーンも稚拙です。特に「ローレライ」の特写は悲ししほど稚拙で、特写であることが見え見えなのです。所詮、日本の特写は縫いぐるみで演じるゴジラの世界なのでしょう。CGの技術の差を評価する能力はありませんが、リアリティに欠ける特写であることは間違いありません。同じ特写でも今上映中の「スターウォーズ」や「宇宙戦争」「アイランド」と比べてみると、その差が良く分かります。
娯楽作品でもない、特写で見せるほどの技量もない。では、何が映画の主題なのでしょうか。北朝鮮の工作員を登場させることで、今の政治的状況を描こうとしているのでしょうか。それにしては、イージス艦の副長(寺尾聡)がクーデターを起こす理由が、「自衛隊の秘密組織に息子が殺された」というのでは思想性もくそもないでしょう。ましてや憂国の防衛大学生がホーム・ページに書いた論文が日本を憂いて、それが北朝鮮の秘密工作員の目に止まり、接触を図ったったというまるで非現実的な設定も噴飯ものです。日本にも優れた政治映画はたくさんあります。いずれも緊張感溢れる映画です。妙な愛国心を煽ることを狙った映画なのかもしれませんが、そうであれば完全に失敗作でしょう。最近、南北朝鮮の問題や軍隊の問題を取り上げている韓国映画を数本観ましたが、正直、韓国映画のほうが圧倒的に面白いですね。
また、政府の対応も、無能な総理大臣と閣僚たちというありきたりの構図から一歩も出ていません。わざわざ韓国の女優をオーデションで採用して使っているのですが、まったく意味のない使い方で、「ちょっと国際色を出して見ました」という程度のものです。それぞれの役柄に現実感がないのも、この映画の最大の”特徴”でしょう。また役者の演技が極めて稚拙です。たとえば、真田広行は自衛官でありながら、いつも体が小刻みに動いていて、とても”兵士”の凛凛しさはありません。何発も銃弾を体に受けながら、最後まで戦い続けるというのも、とてもまともに見るに耐えない展開です。もし映画制作者や監督が、この映画を海外市場を意識して作ったのであれば、どこかで大きな誤解をしているのでしょう。
この映画に期待していたことが1つありました。それは日本人ではなく、アメリカ人のウィリアム・アンダーソンが編集していることです。多くの日本映画にはスピード感が欠けています。それは編集の時に大胆な省略ができないからだと、私は思っています。ですから、アメリカ人が編集した日本の映画がどんなできばえになるか期待していました。しかし、その点でも失望しました。映画の始まりのシーンの緊張感のなさには、苛立ちさえ覚えました。テレビで、彼は「できるだけ日本的なものを生かしたい」と語っていました。その時、「それじゃあ、あなたを使う意味はないでしょう」と思ったのですが、やっぱり意味のない編集になっていました。
私の記憶に間違いなければ、「妖怪大戦争」の製作者(角川映画)は、この映画を国際市場で売り出す計画だそうです。もしそうなら、まったく”誤解”もいいところでしょう。本当に、この映画を国際市場に出そうとしているのでしょうか。まず、ここでもストーリーに娯楽性もなければ、メッセージ性もありません。ましてや時代性は皆無です。今という時代の中で、どういう意味を持ちうるのかというのが、映画のベースになければならないと思います。まさか、夏だから妖怪物、というわけではないでしょう。あえて解釈すれば、現代の使い捨て消費社会に対する批判というのもないわけではありません。ただ、加藤保徳という怪人を登場させ、現代の大量消費文化を批判するようなプロットにしておきながら、それを映画の中で真面目に展開しようとはしていません。妖怪と機械を融合させ、”機怪”を作り出すのはいいのですが、その”機怪”の幼稚さには、まったく失望です。では、娯楽作品かというと、ちっとも娯楽作品になっていない。では、一夏の少年の成長を描いた映画かというと、全然違います。何のために妖怪を出さなければならないのか。しかも、ここでも特写がなんとも稚拙で、「ローレライ」同様失望以外何物でもありませんでした。
韓国映画が、韓国という文化や政治状況をベースに見事なアイデンティティを描きあげ、それを普遍化させるのに成功(たとえば「ブラザフッド」は名作です)しているのに対して、”妖怪”という極めて日本的な存在を材料に”日本的なもの”を売り物にしようとしたのかもれませんが、国際市場ではまったく受け入れられないでしょう。日本的なもののなかに、いかに普遍性を見出していくかが重要なのです。別に日本的なものに拘る必要はありません。そこに人間に共通する普遍性、共通な意識があれば、観客は共感するはずです。日本の文化に誇りを持つのは良いのですが、それが逆に日本的なものに対して歪んだイメージになっているような気がして仕方ありません。日本的というと、すぐに扇子を持ち出したり、特殊日本的な状況を売り物にするのでは、世界の観客の心を魅了することはできないでしょう。ましてや、芸術家としての映画監督としては失格でしょう。
黒澤明にせよ、小津安二郎にせよ、彼らが世界で評価されているの日本的なものの中に人間の普遍性を見出しているからではないでしょうか。日本の国際化が進んでいるのは確かですが、文化という面では、むしろ後退しているのかもしれません。リアリティというのは、別に現実的なことを描けばいいのではなく、非現実的なストーリーやシーンの中にも猛烈にリアリティを感じさせることもできるのです。
では、日本の映画界の何が問題なのでしょうか。映画界の詳しい状況は知りません。予想するに、良い脚本がないのではないでしょうか。良い脚本を書ける人がいないのではないでしょうか。例えば、「七人の侍」は、黒澤のほかに、市川昆、橋本忍(記憶に間違いがなければ)が、伊豆の旅館に泊り込み、じっくり練り上げたものです。ですから、ストーリーに無駄がなく、それぞれの行動、発言が必然であり、緊張感を持続することができるのです。良い脚本がなければ、良い映画はできないのではないかと思います。大手映画会社は、大量宣伝でヒットする映画を作り出すことができるのかもしれませんが、それは長続きしないでしょう。
さらに映画をちゃんと評価するシステムがないのも、映画界にとっては厳しいのでしょう。新聞の映画評には、あまり見るべきものがありません。ちゃんと評論できるシステムが必要なのでしょう。映画評論家が、映画のコマーシャルに出ていても、誰も批判しないのでは、映画評論の世界は成立しないでしょう。評判が良かった映画にタケシの「座頭市」があります。しかし、私は、この映画は最低の映画で、勝新太郎を侮辱するものだと思っています。勝が長年かかって作り上げてきた座頭のイメージ、それは彼の人間観に根ざしたものでした。それは、いわば日本の文化でもあると思います。映画の基調に虐げられた者に対する優しさ、ヒューマニズムがベースにあり、しかも独特なユーモアがありました。それを、タケシの「座頭市」は残酷さ以外の何物もなく、まったく無残にも勝新の「座頭市」を壊してしまったのです。しかし、私が知る限り、そうした評論をした人物は誰も知りません。なぜか理由は分かりませんが。どこから見ても、良い映画とはいえないにも拘わらず、です。
しかし、大作ではないですが、素敵な小品の日本映画もあります。セントルイスの映画祭で「ウォーター・ボーイ」を見ましたが、観客に多いに受けていました。大掛かりなストーリーではないですが、一級の青春映画でしょう。同じ狙いの「スイング・ガール」は、予想よりもできは悪かったけど、楽しませてくれました。また、最近見た映画に「帰郷」(萩生田宏治監督)というのがありますが、これも小品ですがお勧めの映画です。しかし、商業主義に乗らない監督や脚本家は、十分な制作のチャンスも与えられないでしょう。先学期、大学のクラスで学生が書いたレポートでは、世界で最も多くの映画を製作しているのがインドで、次がアメリカ。確か、そのレポートでは、日本は3位にランクされていました。しかし、その多くは観客の目に触れることなく、短期間の上映で忘れ去られているのでしょう。
日本でも映画の作り方が変わってきています。ベンチャー企業風に出資者を募り、利益を還元するというハリウッド式の制作が増えています。しかし、そうした大仕掛けの映画は、リスクも高く、初めから観客の媚びている映画が多いようです。
映画は産業的にも、文化的にも十分に価値のある分野です。しかし、長い間、低迷が続いたことで、映画産業を支える基盤が大きく崩れているのでしょう。世界市場を視野に入れながら、映画を作っていく必要があるのでしょう。しかし、こうした国際分野で活躍できる人材は、圧倒的に不足しているのが、日本の現実です。私が教えたアメリカのワシントン大学は、普通の大学ですが、映画論のクラスがありました。映画フアンとしては、何とか素晴らしい映画ができ、それが世界で受け入れられ、日本の監督や俳優が海外の映画に頻繁に登場するようになればと願っています。このままでは、日本映画は中国や韓国、香港、それに東南アジアにさえ置いていかれるかもしれません。
PS:劇場用アニメはほとんど見ていますが、昨年の押井守の「イノセンス」と、大友克彦の「スチーム・ボーイ」は、いずれも失望しました。宮崎駿の最近のアニメも息切れしており、日本のアニメも限界に近づいているのかも知れません。ちなみにテレビアニメでは12チャンネルの「ガラスの仮面」と4チャンネルの「モンスター」がお勧めです。ただ、「モンスター」はもう終盤なので、途中から見てもストーリーが分からないかもしれません。いずれも火曜の深夜の番組です。
PS2:ダンカンが脚本を書き、監督をした「七人の弔」は、観るに値する映画です。楽しい映画ではないですが、できのいい映画であることは間違いありません。どうもメジャーの映画会社の作る映画は、大金を投じて儲けることばかり考えているようですが、こうしたインディーズ物の映画に可能性を感じます。
1件のコメント
このコメントのRSS
この投稿へのトラックバック URI
http://www.redcruise.com/nakaoka/wp-trackback.php?p=131
現在、コメントフォームは閉鎖中です。
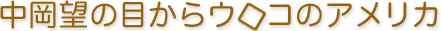



はじめまして、大変興味深く読ませて頂きました。残念ですが、確かに最近の日本映画に見るべきものは少ないと思います。
先日、「ヒトラー・最後の12日間」という映画を見ました。とても見事な映画でした。シリアスな緊張感と息詰まるリアリティがあり、兵士や民間人がボロ雑巾のように死んで行き、最後はヒトラーも死にますが、「死」にしつこさというか、重苦しさが少なく、しかも暗い映画にもかかわらずストーリーが非常に面白く、かつ戦争の悲惨さ、無惨さがまざまざと伝わってくる作品で、見事としか言いようが無いものでした。しかし、同じ敗戦国・日本で、仮に「終戦・最後の12日間」とかいうような映画を作ったとして、同じような名作が出来るかと言えば、多分無理なのではないかと思います。その理由の一端として考えられるのは、これはあくまで私の主観なのですが、日本人の特異な死生観なのではないでしょうか。
以前、ホリエモンことライブドアの堀江貴文社長が「実は僕は、自分は死なないと思っている」などと発言して白い目で見られていましたが、実は多くの日本人は本質的には彼と同じように考えているのではないでしょうか。国民みなが、自分の「死」について真剣に考えようとしない。以前、「死生学」というのを習った事がありますが、自分が死ぬという当たり前のことを前提として若いうちから人生設計を行っている人は、日本では非常に少ないように思われます。人間に限らず、生物は皆、生まれた瞬間から死に向かって時を刻み続けているものなのですが・・・。
「仕方ない」と言って何もしないのも、そのあたりに原因があるのではないでしょうか。自分がいつか死ぬという前提に立てば、仕方ないなどとは言っていられなくなります。ところが、多くの日本人は心の中で自分だけは不老不死だと思っているから、待っていればそのうちいい状況が巡ってくるさ、という奇妙な楽観論に浸っているのではないでしょうか。
話が逸れてしまいましたが、こと戦争を舞台にしたものでは、死というのは絶対に外せないものです。ところが、日本映画では死と言うのが異常で、普通は自分には関係無いものとして描かれているため、死というのが必要以上に暗くて重苦しいものになってしまい、死というシーンにいやでも向き合わざるを得ない戦争映画は、息がつまりそうな重苦しさに満ちたものになっていまっているのではないか・・・私の推論で、根拠も何も無いのですが。
もしそうだとしたら、やはりその原因は宗教観にあるのでしょうね。キリスト教にしろ仏教にしろ、死後に天国や極楽浄土に行ける事になっているわけで、その分、死に対する恐怖が薄れる事になるのでしょう。日本人は実質、ほとんどの国民が無宗教ですから、国民全員で死に対して目と耳を塞ぎ、自分に関係が無い事にしておかないと恐怖で押しつぶされてしまうのでしょう。
ただ、個人的には日本映画にも望みはあると考えています。まず一つ目の理由としては、日本人の評価能力の低さでしょう。黒澤監督の作品にしろ、宮崎アニメにしろ、現在素晴らしいといわれているものはいずれも海外から評価されて、国内で評価が高まったものです。日本人に良い物を見る「目」が無いとすれば、将来日本映画界をひっぱる逸材が「海外の」評論家の評価を待って、眠っているとも考えられます。これまでそうであった以上、これからそうでないという理由はどこにもありません。日本人としては、少し情けない話ではありますが・・・。
もう一つは、実写はともかくとして、アニメ・ゲーム分野における日本の圧倒的な強さです。映画はともかくテレビ放送ワクにおいては、シェアの65%を日本アニメが握っているというのを聞いたことがあります。テレビゲームも、海外勢が躍進しているとはいえ「本家」の日本勢はまだまだ国際競争力を持っています。こういった商業主義的性格が強いものが「文化」と言えるか議論はあるかもしれませんが、例えば現スクウェア・エニックス(旧スクウェア)の「ファイナルファンタジー」シリーズは毎回、海外で数百万本、金額にして200~300億円売り上げています。少なくとも「妖怪大戦争」よりは国際競争力の点で期待を持っていいのではないでしょうか。
PS・もしもう見ていたら申し訳ないのですが、劇場用アニメでは新海誠監督の「ほしのこえ」「雲の向こう 約束の場所」が個人的にはお勧めです。日本アニメ界の新たな息吹を感じさせます。
コメント by 水無月 — 2005年8月24日 @ 12:51