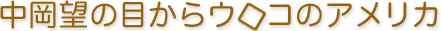バーナンキFRB議長とアメリカの金融政策
この前のブログに「アメリカ経済の悲観的シナリオ」と題する記事を掲載しました。最近のアメリカ経済の動向を見ていると、そこで書いたシナリオが現実のものようになりつつある感もあります。経済は思いもよらない動きをするものです。以前のブログに「アメリカ株の動向」についても書きましたが、そこで展開した見通しも現実味を帯びてきているようです。ぜひ読み返してみてください。今回は改めてバーナンキFRB議長と金融政策に関する記事を掲載します。といっても、この原稿は3月中旬に行なった講演の速記録に手を入れたものです。が、数字的な部分を除けば、今でも十分に読むに耐える内容です。目先の動きに囚われず、大きな流れと枠組みを抑えておくと、それほど大きな判断の誤りはしないものです。長い文章ですが、参考になる部分も多いと思います。
ーお手元に詳しい履歴があるから私からは一言も必要ないと思いますが、バーナンキさんがFRBの新議長になったので、タイミングがいいかなと思ってお願いしたわけです。アメリカの政治経済状況というのは大変面白い時期にあると思いますが、中岡さんは東洋経済でずっと記者生活をやられていて、抜群の英語力を駆使して会社四季報の英文版の編集長や、「Tokyo Business Today」、「The Oriental Economist」の編集長等で活躍されました。私が「週刊東洋経済」の仕事をやった時に、いろんな外国人のインタビューを中岡さんと一緒に行った際、中岡さんが英語の通訳をやってくれて、イギリスの著名な作家ジェフリー・アーチャーやブリティッシュ・テレコム会長などいろんな外国人をインタビューできたのも中岡さんのお陰です。
数年前に東洋経済を辞めてフリーのジャーナリストになりました。東洋経済を辞めたのはあまり宮仕えをするものではないということで、今精神状態は非常にいいということですが、収入はかなり減っちゃったとぼやいています。仕事としては他に国際基督教大学と日本女子大、武蔵大学の講師をやっておられて、それから大阪外語大学など他の大学の講座もたいへん忙しくなってきたということです。今日はレジュメを用意していないのは、レジュメがないほうがかえって面白い話が出来るということなので、楽しみにしていただきたいと思います。唯一の欠点は喋るのが早過ぎることなので、今日は皆さん聞き取れなかったら講演録を後でお読み下さい。今日は少しでもゆっくり喋るように努力すると思います。それではよろしくお願い致します。
中岡 大学で授業をする時は立ってするので座ると何か落ち着かない感じがします。今浅野さんからご紹介いただきましたが、浅野さんには、東洋経済在職中からお世話になってきました。改めて、この場を借りて感謝したいと思います。
1992年のクリスマスの日にアメリカから1本の電話が掛かってきました。それはハワイのホノルルにあるアメリカ政府のお金で運営されている唯一の大学大学イーストウエストセンターからでした。ジェファーソン・フェロセーという奨学金があるから来ないかと。普通は申込書を出して審査を受けて奨学金を貰いますが、どういう訳か、とにかく奨学金をあげるからこいという話でした。そのとき編集局長をしておられた浅野さんに「こういう招待が来ているけれどどうしようか、すぐ僕は答えを出したい。とにかくこの場で返事を貰えないだろうか」と言ったら、即座に「行っていいよ」との返事をいただきました。許可だけではなく「長期出張扱いにしてあげよう」という配慮までしていただきました。今思い出して、これが僕のある意味では人生の大きな転換点になったかなと思っています。
私は東洋経済に在職中の81年から82年にフルブライトの奨学金を貰いまして、ハーバードに1年行きました。でも正直言って、その頃はまだ駆け出しに毛が生えたぐらいの記者で、アメリカ専門と言うのも憚れるレベルでした。それから87年にもアメリカの情報局USIAの奨学金を貰って行きました。ですからイーストウエストセンターの奨学金はアメリカの政府から3度目の奨学金だったわけです。なぜイーストウエストセンターの奨学金が素晴らしいかと言うと、記者としてアメリカに取材に行く時は、日本ですでに取材のアレンジして行くんですね。誰々に会うとか、日本の窓口を通したり、アメリカの出先に頼んでアレンジをするのが普通です。ですからアメリカに取材に行ってもそんなに苦労することはないわけです。
ところがイーストウエストセンターのジェファーソン・プログラムは、まったく違いました。「ジェファーソン」というのはジェファーソン大統領の名前から取られたもので、彼はアメリカのジャーナリズム父と言われている人物です。その関係でジャーナリストを呼んだ特別なプログラムですが、そこに入ると何の面倒も見てもらえず、放り出されるわけです。何のケアしてくれません。ですから、取材をしようと思えば、自分でハワイから本土にいろんな電話をしたり、ファックスを入れたりしなければなりません。1ヶ月ほどアメリカ本土をフィールドワークする機会がありましたが、それも行き先々で電話で取材のアレンジをしなければなりません。先ほど浅野さんから、英語が少し上手いとおっしゃっていただきましたが、ある意味ではその時に鍛えられたというか、度胸がついたといっても間違いではないと思います。それまでは喋れてももう1つ迫力がなかったのですが、そのセンターでの経験を通して英語力が一段上がったかなと思っています。水泳を教える時に海に放り投げればいいという話がありますが、やはり窮すれば通ずで、こうした経験を通して度胸がついてくるものです。
3度ほど奨学金を貰った後、4度目は2002年にセントルイスにあるワシントン大学から、これもある日突然Eメールが入りました。その表題が「Invitation」で、何かいかがわしい文章だろうと思って開かないで置いておいたのですが、ちょっと気になって開いてみたら、大学からの招聘状でした。その時はもう浅野さんは社長を辞めおられていました。当時の社長に話をしたのですが、4度も会社を休んでアメリカに行くのは無理だということで、ちょうどいい人生の転機だと思って2002年4月に会社を辞めて、アメリカに行きました。セントルイスのワシントン大学で大学の様々なプログラムに参加する一方で「東アジア経済の勃興と没落」と題する授業を教えました。
帰って来てから、2004年4月に中央公論から「アメリカ保守革命」という本を出版しました。これはある意味では思想史といいますか、経済の領域を超えた思想史的な、なぜアメリカで保守主義が台頭してきたのかというのを、目先の話ではなくて1940年代から説き起こしたものです。最近、ネオコンとか何とか言われておりますが、それはアメリカの保守主義運動からすると1つのエピソードに過ぎないといのですね。ただ、マスコミは、そうした歴史的な背景を無視して報道しますので、なかなか本当の姿が見えません。今日1冊持って来ました。後で事務局に置いておきますので、どなたかお持ちください。
それから今年の2月2日に経済倶楽部で講演をしました。講演のタイトルは「バーナンキFRB新議長と金融政策の行方」で、長い速記録も出来ております。ですから今日は、そのときの講演と若干オーバーラップするところもありますが、出来るだけ違った角度からお話しできればと思っています。
現在、私は大学で教えております。今年度は4つの大学で9コースを教えます。9コースとも全部内容が違います。「アメリカ経済論」「日本の企業と社会」「国際経済」「日本経済史」と「アメリカ文化研究」の5コースを国際基督教大学で教えます。それから日本女子大では「比較体制論」と「経済概論」。武蔵大学では「東アジアのビジネス」、大阪外国語大学で「日米関係論」と全く違う9つの分野を教えます。様々な分野を教えますが、その中で専門家の顔が出来るかなというのが、アメリカの経済・政治です。経済では、金融や為替相場に関する記事を書くことが多いのですが、私は大学を卒業後、銀行員をやっていた関係で金融に関して感覚的に肌に合うところがあります。その経験から、経済をバランスシートやお金の流れをベースに物を理解するという癖がついているようです。今日のテーマは「バーナンキFRB議長の金融政策」ですが、20年ほどアメリカの金融政策の動きをフォローしてきたのも、そうした背景があったからです。
宣伝をさせていただくと、明日(3/17)発売になる時事通信の週刊誌「世界週報」にアメリカ経済の見通しについて4ページほど書いています。もし機会がありましたら、今日の講演とあわせてご覧いただければと思っています。それと来週の水曜日にサピオという小学館から出ている雑誌「SAPIO」にアリメカの住宅バブルについて4ページほど書いています。今日の話と重ね合わせながら読んでいただければと思っています。
非常にいい時期にこのお話をさせていただくチャンスをいただいたなと思っています。バーナンキ新議長が誕生したことです。彼に関していろんな本が出たり、メディアでも広く紹介されていて、皆さんもある程度の情報はお持ちだと思います。しかし、まだまだ彼の本質的なところ、理論などは必ずしも十分に紹介されていないかなと思います。その意味で、彼の理論的な背景などをお話するにはちょうと良いタイミングだと思います。第二に、世界の経済が変わりつつあるということでし。この2、3年世界は超低金利にありましたが、世界は金利引締めの段階に入りつつあります。アメリカは2004年6月から段階的に金利引上げをやってきて、1月末に14回連続で政策金利であるフェデラルファンド金利の目標水準を1%から4.5%まで引き上げました。日本銀行も量的緩和政策をやめました。それから欧州中央銀行も利上げに踏み切りました。世界経済はこれからどういう形で変わってくるのだろうかと、そういう意味ではアメリカ経済のみならず、日本経済、世界経済も含めて大きな転換点に来ているのではないかと思います。
これは全部話をすれば時間がかかるので、アメリカに集中して話をしたいと思いますが、バーナンキ議長は共和党員です。アメリカでは、多くの人は共和党か民主党に登録します。彼は共和党に登録しています。ブッシュ政権を支えている経済理論は、ある意味では80年代のレーガン政権のサプライサイダーの経済学の流れを汲んでいます。また、マネタリスト的な発想も見られます。ブッシュ政権は2001年と2003年に大幅な減税を行なっていますが、それは明らかにレーガン政権の政策の焼き直しです。ただサプライサイドの経済学は当時ほど人気も影響力もありませんが、それでも保守派の経済思想の基本になっています。バーナンキは共和党員であり、またブッシュ大統領によってFRB理事に任命され、2年間ほどFRB理事を務めたあと、大統領経済諮問委員会委員長に任命されています。今回のFRB議長は、まさに短期間に3段飛びで大出世したわけです。
そこで皆さんに質問ですが、バーナンキは保守派の経済学者だろうか、リベラルな経済学者なのでしょうか。思いつきで結構です。バーナンキというのは保守派の経済思想を代表する経済学者だと思われる方手を上げて下さい。お一人ですか。彼に関するエピソードを1つ言いますと、今アメリカで最も激しくブッシュ政権を批判している経済学者はプリンストン大学のポール・クルーマン教授です。私事ですが、私は中央公論からポール・クルーマンの本「恐慌の罠」という本を出しています。クルーグマンはその本の中で、日本銀行はインフレターゲット政策を取るべきだと主張しています。クルーマンをプリンストン大学に呼んだのは、当時経済学部長だったバーナンキです。学者の世界ですから別に党派性は関係ないかも知れませんが、共和党の立場にあるバーナンキが最も反共和党的なクルーマンを高く評価しているのです。ある保守派の評論家が「バーナンキはケインジアンだ」という論文を書いています。こうしたエピソードからすると、彼はどうも保守派とは言い切れない気がします。
もう1つ、彼の経済思想を判断する非常に大きなポイントがあります。彼は金融政策の研究者であると同時に大恐慌に対する研究者です。彼が書いている2冊の本があります。1冊は1930年代の大恐慌についてのエッセイで、大恐慌の詳細な分析を行なっています。大恐慌の分析で我々がすぐに思いつくのは、ノーベル経済学賞を受賞したミルトン・フリードマンですが、彼はアメリカの通貨史の本を書いています。フリードマンなどのマネタリスト達は「政府やFRBの政策の失敗で大恐慌が起きた。要するにFRBが本来ならマネーサプライを増やさなければならないときに逆に減らしてしまったことが大恐慌を引き起こした」と主張しています。そうした分析から、中央銀行に対する機能を制約し、ルールに従って政策を行なうべきだという主張が出てきます。ですから、極論ですが中央銀行はいらない、昔のような金本位制に戻ればいいという主張さえする保守派の経済学者もいます。すなわち、マネーサプライを重視し、インフレはゼロにしなさいというのが、コンサバティブな、フリードマンに代表されるマネタリストと称される経済学者の基本的な考え方です。
それに対してバーナンキはどうだろうか。もし彼がフリードマンと同じような議論をしているのなら彼はコンサバティブな経済学者と言えると思います。ところが彼が何を言っているかと言いますと、大恐慌が起こったのは政府の失敗じゃない、市場の失敗だというのですね。これはマネタリストの主張と真正面から対立する理論です。もっと言えばアメリカの大恐慌が世界に広がっていったのは金本位制に原因と主張しています。大恐慌が起こった時に金はアメリカとフランスに集中したのです。本来の金本位制ですと、金が入った国の通貨供給量が増えるわけです。そうした国では、金本位制ではリフレ政策が自動的に発動されます。逆に金が流出した国はデフレ政策を取ることになり、景気が悪化して物価が下落するわけです。ところが第1次世界大戦のあと金本位制を離脱して、金本位制が復活するのですが、バーナンキは非常に不完全な形で金本位制が復活してしまったと主張しています。アメリカで金融不安が起こった時にどういうことが起こったかといいますと、個人は通貨を退蔵し始めたのですね。たんす貯金のような形で、通貨が経済から流出したのです。銀行も不良債権が増え、与信を抑制し始めたのです。今の言葉で言うと自己資本を充実したわけです。ですから金の保有量増加に見合った形で通貨は増加しなかったのです。従来の金の量と通貨の発行量の関係が断ち切られてしまった。それれが、大恐慌を引き起こす原因となったのです。その中でバーナンキは、マネタリストと違って、政府が大恐慌を切り抜けるために大きな役割を果たしたと主張しています。ですから保守的な経済学者は政府とか中央銀行の役割を否定する立場ですが、バーナンキはどちらかといえばアクティビスト的なのです。また、バーナンキは、金本位制から早く離脱して、通貨供給を増やした国のほうが、景気回復が早かったとも主張しています。
もう1つバーナンキの思想を判断するエピゾードがあります。それは彼が2002年にFRBの理事に任命された時に、グリンスパンが超低金利政策を取っていました。アメリカ経済は2001年4月からリセッションに陥ります。誕生したばかりのブッシュ政権は大幅減税を行い、グリンスパン議長は大幅な利下げを実施します。財政拡張と金融緩和でリセッションは年末には終ります。戦後で最も短期間のリセッションでしたが、その後の回復の足取りは鈍く、2004年になってアメリカ経済は急激な回復に向かいます。FRB理事に就任したバーナンキは、グリンスパンの超低金利政策を支持しています。彼は、デフレに陥った時のコストがいかに高いか、大恐慌の分析を通して十分に知っていたのです。また、日本のようにバブル崩壊後の中途半端な金融政策がデフレをもたらしたことも知っていました。日本のデフレについて相当研究していました。経済がいったんデフレに陥ったらデフレから抜け出すためにものすごいコストがかかるということを彼は知っていたのです。ですから、彼は論理的にグリンスパンの低金利政策を支持するのです。
でも支持するだけではなく、もっとラディカルな主張をします。本来なら金融政策では長期金利は操作の対象にはなりません。短期金利をコントロールするのが金融政策であって、長期金利は全然違ったファクターで決まるというのが経済学の理論ですが、彼は長期金利の対象にすべきだと主張します。要するに債券市場にも中央銀行は介入しろというわけです。それから政府というのは通貨を発行する特権を持っているのだから、通貨をどんどん増発すればいいとさえ主張しています。場合によっては、ヘリコプターからお金をばらまけとさえ言っています。もちろんそうした主張は現実にはありませんし、おそらく中央銀行の果たすべき役割を強調する意味で、こうしたレトリックを使っているのだと思います。要するに、異常な状況に関しては異常な政策をとって然るべきであるというのが、彼の考え方なのでしょう。これは明らかに中央銀行の役割を非常にポジティブに評価しています。
そうすると伝統的なマネタリストとか保守主義者とは基本的に考えが違うのです。例えばフリードマンは中央銀行はパッシブな政策を取るように主張しています。彼は「X%ルール」というのを主張したことがあります。それはくマネーサプライをとにかく「X%」で機械的に増やすべきだという主張です。恣意的に通貨供給量を操作するなということです。また、マネタリストはゼロ金利、ゼロインフレーションか一番好ましいと言っています。要するに、マネタリストやアダム・スミスなどの古典的な経済学者は、実質経済を問題にして貨幣経済をあまり意識しないところがあって、彼らが考えるのは“相対価格”なのです。インフレをゼロにして、生産性を反映して価格が下がればいい。相対価格が変わることによって経済の構造が変わってくるというのが、フリードマン等のマネタリストの考え方です。
それに対して、バーナンキは「インフレターゲット論」の強力な推進者です。インフレターゲット論というのはゼロ・インフレを主張せずに、“ゆるやかなインフレ”を主張します。これはマネタリストの理論と基本的に違います。ということを考えると、バーナンキはケンジナンじゃないかという主張も出てきます。たしかに、彼が主張する金融政策を見る限り、どちらかと言うとケンジナンのポリシーパラダイムで金融政策を考えているのではなかろうかというところがあります。そうすると彼がこれからやっていくだろう金融政策が1つ見えてくるわけです。
もう1つバーナンキに対するエピソードを言いますと、ノースキャロライナか何処か行って労働組合を対象にして講演をしています。その時に彼は「アウトソーシングによってアメリカの労働者は職を奪われている。そういった状況に対して政府は対応を取るべきだ」と主張しています。これもどちらかというと、ケインジアン的な発想です。バーナンキの前に大統領経済諮問委員会委員長だったマンキュー現ハーバード大学教授は、委員長当時、「アウトソーシングは悪くない。むしろいいことで経済のロジックに合っている。企業がアウトソーシングするのは悪くない」という議論をしました。それは共和党の政治家の大反発をくいまして、結局彼は追われるようにして委員長を辞任して、ハーバードに戻るわけです。バーナンキの主張は、新古典派的な立場からずれば、当然の主張です。しかし、バーナンキは、単に経済ロジックに従ってアウトソーシングをしたって構わないというロジックではなくて、やはりそこには労働組合に対する配慮を見せています。どう考えても彼の発想というのは、新古典派的な発想と言うより、むしろどこかケインジアン的な発想を持っている経済学者かなという気がします。ただこれはまだ分かりません。これは私がエピソードや彼の議論、スピーチを元に私が下した1つの評価です。これからバーナンキはいろいろ発言をするでしょうが、今話したことを心のどこかに留め置いていただいて、彼の発言を聞くときの判断基準の座標軸になると思います。
彼はリベラル派だという感じがします。ですから非常に硬直的なマネタリスト的な政策を取るのではなく、絶えず雇用と物価を両睨みしながらやっていく。「インフレ・タカ派」と「インフレ・ハト派」という仕分けの仕方があります。ブッシュ大統領が彼をFRB議長に選んだ1つの理由は、彼が「インフレ・ハト派」だからと言われています。政府はどちらかといえば金融を引き締めてもらいたくないという本能を持っています。景気の方に視点を移した金融政策を執ってほしいというのが、どの国の政治家も共通に持っている気持ちです。政治家は金融緩和政策を歓迎するものです。ですから日本でも量的金融緩和政策を解除するかしないか、利上げをするかしないかという時に、政府の方はデフレの状況というのは解消されていない慎重な姿勢を取るべきだと主張したのも当然なのです。選挙を考えた時に、政治家は若干のインフレがあってもいいから高成長を期待するものです。ある意味ブシッュも今年11月に中間選挙があるわけですから、出来ればこれ以上金融を引き締めてもらいたくないという本音があったのではないかと思います。そういった意味では「インフレ・ハト派」の彼をFRBの議長に選んだという議論もありますが、確かに一面当たっているかなとも思います。これも時間をかけて見てみないと分からないところがあります。
実は3月27日と28日にFOMC連邦公開市場委員会というのが開かれます。これは初めてバーナンキが議長になって主催するFOMCです。恐らくここで利上げをするのかしないのかということで、今後の彼の金融政策のスタンスがかなりはっきりしてくるでしょう。もう1つはどういうコメントが出て来るかによって状況が変わってくるので、また新しい判断材料が出て来るのではないかと思います。
彼が議会で承認されたのは12月ですが、そのあと市場では利上げは打ち止めという雰囲気が出て来ました。その結果、為替市場で円が高くなり、1月の中旬ぐらいまで円高の水準が続きました。その後、FOMCでもう1回金利を上げるかなという見方が強くなって来ています。それで再びドルが強くなり、円が安くなりました。マーケットは敏感に彼がどういった金融政策をとるかということを注目しながら、マーケット・オペレーションをやっているのです。いわば、FRBの金融政策に対する思惑が、為替相場に大きな影響を与えているのです。
私は、彼は今度再び利上げをすると見ています。0.25ポイントぐらいの利上げはするのではないかと見ています。アメリカの最近のエコノミストやアナリストの分析を見ていると、フェデラルファンド金利は5%まで引上げられるというのがコンセンサスになっています。アメリカの経済指標はずいぶん強い経済指標が出て来ています。第1四半期の経済成長率は5.5%前後に行くのではないか。ただ去年の第4四半期は1.6%と非常に落ち込みましたが、これは自動車販売が落ち込んだのが最大の理由で、個人消費そのものはそんなに大きく落ち込んでいるわけではありません。というのは去年の中旬ぐらいまで自動車会社は猛烈な販促、特に従業員に対する割引販売をやっており、その結果相当需要の先食いをやって、その反動が第4四半期に出たのです。第4四半期の1.6%というのは一過性のものです。自動車販売も年が明けてかなり正常に戻ってきて、そうすると第1四半期は5.5%ぐらいの成長になってくる。
そうすると少なくとも今の状況で雇用状況もあらゆるものを含めて考えて、3月27日、28日に開かれるFOMCではバーナンキは利上げをしてくるだろうと見ています。それはどういう形で影響してくるかというのは後で述べるとして、その前に教科書的な話になるかも知れませんが、改めてアメリカの中央銀行制度というのはどういうものなのかという話をしたいと思います。
日本には日本銀行があって、フランスにはフランス銀行がある。ドイツにはブリテスバンクがあり、イギリスにはバンク・オブ・イングランドがある。みんな中央銀行にはなんとか銀行という形がつきますが、アメリカでは連邦準備制度が中央銀行で、政策決定機関が連邦準備制度理事会です。連邦準備制度理事会は、調査機関であり、意思決定機関であって、中央銀行が行っているような通常のオペレーションというのは全く行っていません。通常のオペレーション、例えば市場介入や為替介入、銀行に対する融資は連邦準備銀行が行っているわけです。アメリカはワシントンに連邦準備理事会があって、全国を12に分けて、各地域に1つずつ連邦準備銀行がおかれています。もともとアメリカには中央銀行がなくて、連邦準備制度が出来上がったのも1920年代で、日銀よりも発足は後なのです。連邦準備法が制定され、それに基づいてワシントンに連邦準備制度理事会がおかれた。当初、連邦準備制度理事会は財務省に間借りをしていたのです。連邦準備制度理事会が設置された時に12の連邦準備銀行が作られた。では、なんでこんな複雑な制度が出来上がったのでしょうか。
その前にもう1つ、アメリカというのは、これは政治も文化もあらゆるものに絡んでくるわけですが、アメリカでは2つの勢力が絶えず対立しています。それは「中央集権派」と「地方分権派」です。アメリカは、伝統的に地方分権派が強かった。どうして地方分権派が強かったかと言うと、1つには連邦制という“建国の理念”がありますが、もう1つはアメリカはもともと農業国家で、農民や中小業者が大きな勢力を持っていた。その人達は中央政府に対して強い不信感を抱いており、地方の独立性を求める傾向が強かったのです。それに対して都市部における産業家や金融家は中央政府の強化を求めたわけです。産業発展を図り、全国市場を作り上げるには、強力な中央政府が必要だったのです。アメリカ建国の時、どういう国を造ろうかという大きな議論がありました。1つはヨーロッパからの政治的介入を阻止するため強力な中央集権国家を造るべきだというグループがいました。もう1つは、建国の理念というのは地方の独立や連邦制であると主張するグループがいました。彼らは、権力分散こそが建国の理念であるという考え、この考え方は中央銀行設立に際しても大きな論点となりました。要するに、中央集権的な中央銀行を主張するグループは、アメリカで産業革命が起こり、産業が発展する中でナショナルマーケットが出来上がってくるなかで中央銀行制度が必要だと主張しましたが、地方の中小企業家や農民はこうした考え方に猛烈に反対しました。その結果、制度としての中央銀行制度は出来上がらなかったのです。
では中央銀行制度が出来上がらなかったのに、どうしてアメリカが近代国家として機能し得たのか。1つは金本位制です。保守的な経済学者は金本位制やリアルバンキング制度はアメリカにとって非常に好ましいと考えていました。現在においても一部の極めて保守派の人達は、金本位制に復活すべきだと主張しています。アメリカは、金本位制に基づいて銀行制度が出来上がって来た。どういうことかと言うと各銀行が自分の金保有ベースにして、金と交換出来る“兌換券”を発行したわけです。地域的に兌換券は流通するが、なかなか全国的に流通しなかった。ドルという全国的な統一通貨ができるのはかなり後になってからです。金融機能はどう機能したかと言うと、銀行が兌換券を発行し、それが取引の決済に使われた。しかし中には経営危機に直面する銀行も出てきます。近代的な金融制度では、中央銀行が“最後の貸し手”として登場しますが、初期のアメリカの金融制度ではクリアリングハウス(手形交換所)が、そうした役割を果たしていたのです。大きな金融危機が起こるとクリアリンクハウスの手に負えなくなります。その時に、ニューヨークの大手の金融機関が中心になってコンソーシアムを組んで緊急資金の援助をしました。例えばその中で一番有名なのはJ・P・モルガンです。大きな全国的な規模の金融危機が起こった時には、ニューヨークの大手の金融機関が中心に特別融資や救済をしたのです。ところが1920年代の金融危機でもはやJ・P・モルガンをしてもどうしようもない事態が起こった。そこで初めて中央銀行制度が必要だという認識が広がり、連邦準備制度が出来たのです。
その時、なぜ欧州のような中央銀行制度を作らなかったのかというと、依然として中央集権的な中央銀行に対する強い反対があったからです。その反対への妥協策として出てきたのが、ワシントンに連邦準備制度理事会を置き、地方に12の連邦準備銀行を置くという制度でした。ですから連邦準備制度が成立した当初は、実際上の金融政策を取り仕切っていたのはニューヨーク連邦準備銀行だったのです。ニューヨーク連邦準備銀行は独自の判断で市場オペレーションをやっていました。ですから場合によっては、ワシントンの連邦準備制度理事会とニューヨーク連邦準備銀行総裁が権力争いを展開することもありました。どちらが政策のイニシアチブを取るかを巡って対立があったのです。初めのころは非常にプリミティブな状況にあった。そういう状況で金融恐慌が大恐慌へと発展して言ったのです。大恐慌に対してある意味で明確な形の政策が対応出来なかったというのは、政治的な対立、政策に対するヘゲモニーを巡るワシントンとニューヨークの対立があったのです。そのうえ、十分な金融理論も出来上がっていなかった時代ですから、連邦準備制度理事会も結果的には適切な対応が取ることができなかったわけです。
長い間、連邦準備制度理事会も大した力がありませんでした。建物さえ持っていなかった。理事会は財務省に間借りをしており、現在の連邦準備制度理事会のビルを建築したのはルーズベルト大統領です。ニューディールの時に出来た。それまでは理事会は財務省の影響下にあり、理事会の議長も財務長官が兼任していたのです。FRBは政策的な自由もなく、やがて大恐慌が始まり、第二次世界大戦が勃発します。大恐慌を克服する手段となったのは戦争でした。戦争中にFRBに課せられた義務は、戦時国債の価格維持でした。要するに利払いを増やしたくない財務省は、財務省証券の金利が上がるのを嫌がったわけです。そういった意味で財務省証券の買い支えをFRBにさせたのです。長い間、FRBは金融政策の自由度をほとんど持たなかった。それが1951年に財務省とFRBの間で合意が成立して、もうFRBは国債を買い支えなくてもいいですよという議論になりました。この合意は「アコード」と呼ばれています。
戦後になって初めて今のような、近代的な意味で連邦準備制度が出来上がった。FRBが自立性を獲得した後も、政府や財務省とFRBが対立する事態が何度も起こっています。たとえば、ボルカーがFRB議長だったとき、レーガン政権のリーガン財務長官がFRBに利下げをするように圧力をかけました。最初、ボルカー議長はリーガン長官の圧力に抵抗したのですが、最終的に妥協して利下げに応じます。それからグリンスパンが1990年代の初め、金融引き締めをしました。湾岸戦争の前後です。その結果としてブッシュ政権(父親)の再選が阻まれてしまったのです。その時も政府とFRBは対立しました。そういう形で絶えず政府とFRBは緊張関係にあるわけです。その意味でバーナンキが、これからブッシュ政権に対してどういう対応をとっていくのかも、これから金融政策を見る際の大きなポイントになるかなと思います。
バーナンキとグリーンスパンの話を少し触れておきたいと思います。グリンスパンは1987年に議長に任命されてから今回まで非常に長期にわたって、レーガン、ブッシュ政権と2つの共和党政権と、クリントン政権8年、今回のブッシュ政権と非常に長期にわたって最高権力の座に座り続けたわけです。グリーンスパンにはカリスマ的な影響力がありました。グリーンスパンとバーナンキを比べると、グリーンスパンは学者ではなく、もともと産業アナリストでありコンサルタントでした。彼はニクソン大統領の選挙運動のスタッフとしてワシントンにやってきました。それからずっとワシントンに居続けた人物ですが、どちらかというと直感的に物事を判断するという独特のマーケットに対する感覚を持っています。卓越した景気判断をベースに、自分の立場と影響力を強めていった人物です。FRBの中でも圧倒的な影響力があって、彼に面と向かって物を言う人物はほとんどいなかったのです。彼の周りに局長クラスで数人のスタッフがいて、この人達はバロン、伯爵といわれて、非常に内輪の世界を作り上げていました。グリーンスパンは絶対に自分で自分の政策を説明しません。
グリーンスパンは「もし私の言葉を皆さん理解できたとしたら、それはたぶん私が何か言い間違いをしたからです」と言っています。自分の言葉は難解で理解できないのです。彼の一番有名な言葉に「根拠なき熱狂」というのがあります。これも、どう解釈すべきかいろいろ議論されました。マーケットはグリーンスパンの言葉の真意がどこにあるのか、いつも必死に理解しようとしていたのです。
それに対してバーナンキはものすごくストレートに物を言う人です。これは金融政策のスタンスの違いに表れてくると思います。たぶんバーナンキは自分の考えで押し切るというよりも、FRB内のコミュニケーションやマーケットとのコミュニケーションを大事にしながら、そこで政策を立案していくというタイプだろうと思います。ただ歴史的に見るとグリーンスパンは非常に大きな役割を果たしています。FRBの政策決定プロセスに関して、グリンスパンは結果として非常に大きな影響を与えています。1990年代初め、下院にゴンザレスという銀行委員会の委員長がいました。彼は民主党ですが、猛烈にFRBに情報を公開するようにプレッシャーをかけました。FRBは透明性に欠ける。透明性をもっと確立しなきゃいかんと、FRBに対して、特にグリンスパンに対してプレッシャーをかけました。例えば政策決定機関としてFMOC(連邦公開市場委員会)があります。現在、FMOCが開かれてから3週間後に「ミニッツ」と呼ばれる議事録が発表されます。昔は何の発表もありませんでした。それを発表するようになったというのが、グリーンスパンからです。ただ、当初、FRBは議事録の存在そのものを否定するなど、情報公開には消極的でした。
もう1つは日本の金融政策を我々が議論する時に、公定歩合が上がったか下がったかを議論しますが、アメリカもそうでした。80年代までは公定歩合政策が上がったか下がったかという議論をいつもしていました。ところが公定歩合というのは金融政策上あまり意味がないのです。公定歩合というのは銀行が中央銀行にお金を借りる際の金利です。基本的に銀行は中央銀行にお金を借りるということをしません。そうしなきゃいけないということは、銀行のクレディビリティ(信頼性)は完全に崩れてしまいますから、よほど危機的な状況でない限り中央銀行借入はしません。日本は昔オーバーローン、オーバーボローイングというのがあって、都市銀行は日銀から巨額の資金を借りていた時期がありましたが、基本的には資金や準備金が足りなくなった時は、インターバンク市場で借ります。日本ですとコール市場から、アメリカではフェデラルファンド市場から借りるわけです。銀行の中で余資を持っている銀行はフェデラルファンド市場でそれを運用します。リザーブが足りないときも、フェデラルファンド市場で資金調達をするのが普通です。そこの資金需給というのが金利を左右します。
FRBも、実は、公定歩合ではなく、フェデラルファンド金利の操作を通して金融政策を行なっていたのです。しかし90年代の初めまでは、FRBはそのことを何も言いませんでした。ただ公定歩合を上げた、下げたという発表しかせず、理由も発表しませんでした。そのため、金融機関は、FRBの公開市場でのオペレーションを見ながら、政策の変更を推測していたのです。それが90年代になって、フェデラルファンド金利の目標値を発表するようになりました。FOMCが開かれた後にニュースリリースが発表されますが、その最初にフェデラルファンド金利変更の理由が説明されています。その後に、公定歩合を引き上げたか、引き下げたかが追加的に説明されています。ですから、今では公定歩合を議論することはまったくなくなり、フェデラルファンド金利が重要な指標となっているのです。
制度的な説明をしますと、用語として、FOMC、FRB、公定歩合、フェデラルファンド金利の4つが出てきました。これはどういう関係にあるのか、ちょっとややこしいですが、説明します。FOMCは連邦公開市場委員会の頭文字を取ったもので、フェデラルファンド金利を決定する機関です。これを構成しているのは7名のFRB理事と、12の連邦準備銀行の総裁のうちの5名の合計12名が投票メンバーとなっています。FOMCは、年に8回開かれます。開催日も事前に決まっています。12の連銀総裁というのはFOMCのメンバーですが、そのうちの5人の総裁が持ち回りで1年ごとに投票メンバーになります。FOMC議長はFRB議長バーナンキが務めます。副議長はニューヨーク連銀総裁と決まっています。ここ2人は常任で代わりません。ですから連邦準備銀行の5人の総裁の一人はニューヨーク連銀総裁なので、あとの4人は残りの連銀総裁の持ち回りになります。投票メンバーでない連銀総裁も政策を巡り議論には参加することができます。経済情勢などを巡る議論などを行なって、最終的にFOMCで投票によってフェデラルファンド金利に関する決定が行なわれます。
では、公定歩合政策はどうかと言うと、公定歩合を決める権限はFRBにあります。FRBも決めるのではなく、連銀総裁の提案を受けて決めます。どこかの連銀総裁が公定歩合を上げるべきであるとか、下げるべきであるとか提案し、それを受けてFRBで採決をする。ですからFRBとFOMCは違った機能を持っているのです。今はほとんど一体化していますが、昔はそれがバラバラになっていました。ですから非常に面白いエピソードがあります。FRBと地方連銀との間の権力関係があって、FRBが連銀の要請を受けて公定歩合を変更したのですが、ある連銀はその決定に不満の意思表示をするために実施日を意図的に1日ずらして抵抗をしたこともありました。そういった意味で必ずしもFRBが絶対的な権力を持っているわけではなく、FRBと連銀総裁の合意の中で金融政策が決まってくるのがアメリカのやり方です。
もともと金融政策というのは、どちらかと言うと密室で決められてきたわけです。ですからマーケットというのは、FRBが何を考えているのだろうかと一生懸命に推測をしながら自分のポジションを取ったり、いろんな取引を行ったりしたわけです。政策決定プロセスは90年代に入ってかなりオープンになって来ました。政策手段であるフェデラルファンド金利を明確な形でターゲットレートという形ではっきりと出すようになりました。FOMCはフェデラルファンド金利の目標値を決めたあと、「ディレクティブ」と呼ばれる指示書を決定します。その指示書はニューヨーク連銀のトレーディングデスクに送られ、トレーディングデスクは指示書に基づいて公開市場操作を行なうのです。公開市場操作を通してフェデラルファンドレートをFOMCが定めた水準まで誘導するのが金融政策のやり方です。
実は日銀も同じことをやっています。今でも日銀は公定歩合を重視しているようですが、実際の金融政策はコール市場を通して行なっています。コールレートをコントロールするわけです。コールレートをコントロールするために公開市場操作で証券や手形を売買して、市場にリザーブを供給しているのです。
すこし横道にそれますが、日本の量的緩和政策はそういうコンテストでどのように考えればいいかと説明します。もともとゼロ金利政策というのは何かと言うと、公定歩合を引き下げるだけでなく、コールレートを限りなくゼロにすることです。公開市場操作を通して市場に資金を供給して、金利を引き下げることです。コールレートの変動はまず銀行の採算に影響を与えて、それが銀行の信用創造に影響を与えることになります。コールレートが低下すれば貸し出しが増えていくというのが、通常のパターンですが、デフレの状態の中でそういうことが起こらなかったのです。名目金利を幾ら下げても、実質金利が高かったこともありますが、本来働くべき金融機能が働かなかったわけです。それで日本銀行はどうしたかと言うと、日本銀行は銀行の日銀に持っている口座の預金残高を強引に増やすことを決めたのです。銀行が債券を日銀に売ると、日本銀行はその銀行の口座に代わり金を振り込みます。その預金口座には利子がつかないので、残高が膨らんでいくということは銀行の採算上好ましくないわけです。これも正常な状況では、銀行は資金を有効に運用しようとして貸し出しを増やしたり、コール市場で運用したりします。しかし日本のデフレの状況の中においては、そういう状況が起こらなくなりました。日本銀行は何をしたかと言うと、債券を買い続け、銀行の残高を強引に増やす政策を取ったのです。それも、目標残高を設定して、公開市場操作を通して資金を供給したのです。これが量的緩和政策です。30兆円とか40兆円という規模で銀行の預金が増えていったのです。通常の金利政策が効かないから、強引に量を増やして貸し出し(マネーサプライ)を増やそうとしたのが、量的緩和政策です。その結果、膨大な流動性が市場に溜まっているわけです。日本銀行は、いつかマーケットに出て来たら、インフレになることを懸念していたのです。だから出来るだけ早くその異常な量的緩和政策を止めて、金利政策に戻りたいというのが、日本銀行の考え方です。
金融政策は公開市場操作を通して行なわれますが、政策決定の透明性を高めることが重要になってきました。それが90年代のグリンスパン政権の元で行われた1つの大きなポイントです。この透明性を高めるということは、もう1つ非常に大きな理論的な問題に絡んで来ます。バーナンキはインフレターゲット政策を擁護する人物の一人と目されています。ではインフレターゲット政策って何だという議論が出てくるわけです。日本銀行はインフレターゲットという言葉を聞くだけで嫌がっているみたいですが、実はインフレターゲット政策というのは現実にはイギリス、カナダ、オーストラリア、欧州中央銀行、他の先進国で既に導入されています。インフレターゲット政策は判りにくいのですが、バーナンキ流に解釈すると、実は市場とのコミュニケーションを重視する政策なのです。彼が言っているのは、インフレターゲットというのは強引にインフレを抑え込むというのではなく、中央銀行がどういう政策を持っているのか、政策に対してどれだけコミットメントする覚悟があるのか、そういうことをちゃんと市場に伝えることによって市場が正確なインフレに関する予想形成が出来るようにすることなのです。インフレに対する正確な予想形成ができれば、長期金利が安定してきます。それは、経済というのは非常に安定してくるというのが、インフレターゲット政策のエッセンスなのです。ここに中央銀行の公開性と透明性が絡んできます。
ですからバーナンキは、中央銀行の政策の意図、政策の目的、政策の手段に対して透明性を高めていかなくてはいけないと繰り返し主張しています。そのプロセスにおいて市場とコミュニケーションしなければいけない。市場が正確に中央銀行の考え方を理解してくれれば、それに基づいて将来に対する正確な予想を立てるだろう。そうすれば将来に対するインフレリスク等、様々なリスクが低下してくる。このことによって健全な長期的な持続的な成長のベースが出来上がるというのが、インフレターゲット政策のメッセージなのです。
実はグリーンスパンは結果的にはFRBの透明性をずいぶん高めてきましたが、彼自身は非常にイヤイヤやっていたようです。ですから、グリーンスパンはインフレターゲット政策に批判的でした。これはまさに日銀と同じで、特定のインフレ率を設定することは、弾力的な運用の手足を縛ることになると主張しています。FRB理事にコーンという理事がいまして、これはもともとFRBの局長から叩き上げでグリーンスパンの推挙で理事になった人物です(最近、FRB副議長に任命されました)。彼はグリーンスパンが組んで、インフレターゲット政策を批判しています。バーナンキはFRB理事のとき、インフレターゲット政策を採用すべきだと主張したようですが、結果的に受け入れられませんでした。ただ、彼がFRB議長に就任したことで、現実的にはもうそちらの方向に動き始めることみなるでしょう。ただそれをフォーマルな形でインフレターゲット政策にするかどうかは別ですが、いろんな連銀総裁やFRB理事のコメントを見ていると、インフレターゲットという言葉が結構出てきています。
つい最近、サンフランシスコ連銀総裁ディエレンという女性の総裁が、コア・インフレは1.5%が好ましいという発言をしています。コア・インフレは、変動の激しいエネルギーと食料品の価格を除いた消費者物価のことです。バーナンキ議長ははっきりとは言わないのですが、たぶん2%が好ましい水準だと考えているようです。
バーナンキは、インフレ率を設定して、それに向かって中央銀行は目標を達成すると決意を表明し、それによって市場の中央銀行に対するクレビリティを高めることができると主張しています。もう1つ面白い言い方をしているのは、インフレターゲットの設定は“範囲”ではなく“点”でなければならないと言っています。2%から3%というような範囲は駄目で、2%とか2.5%というように明確に設定しなければ駄目だと言っています。それも中期の目標を出さなきゃ駄目だ。それは確実に守るというコミットメントを明確に市場に伝えなければいけない。そのためにマーケットにたくさんコミュニケートしなければいけない。グリーンスパンはカリスマ性の中で金融政策を実行しましたが、バーナンキはどちらかと言うとコミュニケーションを通しながらお互いのコンセンサスを作り上げていくというタイプです。彼がFRB理事だった2002年から2004年までの2年弱の間に数え切れないほどの演説を行なっています。その時に彼の議論を読んでみますと、非常に解りやすい。私はグリーンスパンの演説を何度か訳したことがありますが、訳不可能みたいなのがたくさんありました。どう訳したらいいかわからない。意味が解らない、ロジックもよく解らない。ところがバーナンキの演説を訳していると、ロジックや物の考え方が非常にはっきり解ります。そういった意味では彼はコンセンサス・ビルダーだといえます。彼は、カリスマ性ではなくてFRBの中での議論を通して決定されたことをどんどん外に出して説明すべきだと言っています。そういったことをやりながらマーケットに影響力を与えなさいと言っている。その点ではグリーンスパンとは全く違ったタイプの議長なのです。
たぶんこれから出て来る方法というのは、例えばFRBは2月と六月に2回、ハンフリー・ホーキンス法に基づいて議会に対して金融政策報告を出さなければいけません。その中でFRBの成長率予測も出さなければいけません。以前は、FRBはその年の経済予測しか出しませんでした。しかし90年代にはいって今年と来年の2年予想を出すようになっています。バーナンキはFOMCで毎回経済予測を論議しているので、FOMCが終わった段階でその議論を発表しろと言っています。彼のメッセージは非常にはっきりしていて、自分達が考えていることを隠さず、それをオープンにして自分達がコミットメントすることによって、期待形成に影響を与える。期待形成に影響を与えることによって、景気・金融政策の効果をより効率的にしていく。経済が大きく変動するのは、期待値が変わるのだ。インフレ期待が高まれば長期金利は上がってしまいます。期待が大きく振れることによって、経済状況は大きく変わってきます。こういう考え方は今の経済学のある意味本流になりつつあります。情報理論に基づいた形の政策理論というのは、経済学の非常に大きなメインストリームになりつつあるのです。
実は20年前は全く逆の議論を経済学者はしていました。マネタリズムや合理的期待論は70年代から80年代に非常に大きな力を持った経済理論ですが、その経済理論の中ではバーナンキの主張とは逆に、市場に中央銀行の政策を読まれたら政策効果がなくなると主張されていました。金融政策はいつも“サプライズ”、驚きでなくてはいけないということです。市場の意表をつくようなかたちで金融政策を発表しないと、金融政策の効果はないというようなことが70年代80年代の経済学会の主流の主張であり、現実にそういう政策が行なわれていました。ですから直前まで下げるか上げるか、マーケットはそのまま憶測を重ねていったわけです。それを商売にしていた人がたくさんいました。今はグリーンスパンの場合、市場に対して情報を発信し、市場が対応したときに、追認するように政策を変更するというやり方を取っていました。ですから、それはバーナンキの主張に近いところがありましたが、ただ明確なメッセージを送ったわけではありません。市場は、グリーンスパンの言語明瞭意味不明のメッセージを懸命に解釈し、アジャストメントしていたのです。そういう方向に90年代後半から移っています。金融政策のやり方が移ったわけですが、バーナンキはさらにもう1歩進め、もっとリアルな形で自分達の情報を与えることを主張しているのです。そのことによって、大きな流れの中の期待係数そのものに影響を与えることによって経済の変動を小さくしようというのが、バーナンキの考え方です。
ですからどうも大きな誤解があるようですが、日々の操作はどうするのかという疑問が出てきます。中期的に2%という目標は出した。じゃあ2%から離れては駄目なのかという議論が出てきます。それを根拠に、インフレターゲット政策を採用すると中央銀行の金融政策の自由度が拘束されるのではないか、臨機応変な対応が出来なくなるのではないかという反対論が出てくるわけです。それに対しバーナンキはこういう言い方をしています。「自分達のインフレターゲット政策とグリーンスパンの金融政策の違いはどこにあるか、基本的にない」と。その背後にある経済哲学は全く同じであると言っています。彼は、グリンスパンの金融政策を予防的引き締め政策(プリエンティブアタック・ポリシー)と呼んでいます。このプリエンティブアタックというのはブッシュ政権が使っている言葉で、テロリストに対して予防的な攻撃を加えることを意味しています。テロがアメリカを攻撃する前にテロリストをやっちゃえというのがアメリカのブッシュ・ドクトリンです。グリーンスパンの政策は、様々な経済指標を観察しながら、インフレの予兆が現れたら、すばやく芽を摘むという予防的政策だといえます。インフレの徴候が少しでも出て来たら、もぐら叩きのようにどんどん叩く。現実にグリーンスパンがやって来た政策というのは、そういう政策だったのです。実はバーナンキの言うインフレターゲット政策も基本的な発想は同じです。長期的な目標は立てるが、インフレの兆しが出てくればそれを事前にチェックしていく。
必ずしも硬直的に毎期、毎月、毎週2%を維持しなければならないと言っているわけではないのです。ある程度平均値でそれを達成すればいいと。ただし現実のオペレーションのやり方とすれば、グリーンスパンと同じように予防的な攻撃を加えていく。徴候が出ればそれを抑えていく。そういった意味では基本的にインフレターゲット政策と、従来型の政策というのは基本的なやり方も変わりません。何か変わるかというと、市場とのコミュニケーション、政策的に市場の期待値に影響を与えていくという考え方に違いがあるだけです。というのが、バーナンキが言うインフレターゲット政策です。そうすると、それに合わせて銀行や企業は予想を形成して、資金予想を作ったり、資金計画を作ったりすることが出来るようになります。そのことによって金融的な攪乱要因というのがなくなってくるというのが、彼の政策理論です。
ではFRBが早急に正式な形でインフレターゲット政策を導入するかと言うと、ちょっとトーンダウンしています。バーナンキは、議会での承認のために公聴会でFRB内で慎重に議論を重ね、皆のコンセンサスを得てから決定すると言っていました。
それに対して日本銀行は全く感情的な反発をしていて、リファレンスや目標を出すことに対しても抵抗しています。しかし、世界はインフレターゲット政策の方向に動いています。それは金融理論そのものが大きく変わってきていて、単に量的なオペレーションではなく、金融政策の一番大きな観点というのはインフレ期待にどういう影響を与えるのかということが金融政策のエッセンスだという方向に金融理論が来ています。単に資金の需給関係をコントロールすればいいということではありません。それは実際インフレターゲット政策の大きなポイントになって来ていると思います。
そらからもう1つ、これはアメリカの金融政策の経済の先行きに関わる問題ですが、詳細については明日発売になる世界週報と、来週のサピオにかなり詳しく書いてありますが、アメリカの景気を占う最大のポイントは何かと言うと、住宅バブル問題です。バーナンキは、住宅バブルに対して「金融政策というのは特定の資産の価格をターゲットに運用するものではない。特定の資産の価格というのは市場が決めるものであって中央銀行よりも市場の方がよく知っているはずだ」という言い方をしています。どういうことかと言うと、彼は住宅バブルもしくは住宅価格の高騰に対してなんらかの金融政策を発動する気はないし、やるべきではないということです。
それでは住宅バブルなのかどうなのか、ということです。実はバーナンキはこれを住宅バブルだとは認めていません。確か10月だったと思います。彼が次期FRB議長に指名される前に大統領諮問委員会の委員長として両院合同委員会で証言しています。そこで住宅バブルについて質問されています。彼は「今住宅価格が上がっているのは金利が低いこと、個人の所得が増えていること、世帯数が増えていることためで、決して住宅価格は異常に高いわけではない。この高さもやがて沈静化していくだろう。今年の経済成長率は去年より比べて若干減速するであろう。景気減速に合わせる形で住宅市場の過熱感も少し収まって来るだろう」と言っています。もっと言えば株価だろうが、不動産であろうが、住宅であろうが、特定の資産の価格を自分達の金融政策のための1つの基準にはしない。一般的な物価水準は問題にするが、特定の資産価格は金融政策の対象ではないと言っています。
ところがグリーンスパンは面白いもので、逆のことをやっています。彼は90年代株が下がったら必ず利下げを行ったのです。だからいつも彼は株式市場では救世主、ホワイトナイトでした。だからそういった意味ではグリーンスパンの歴史的評価はこれからなのでしょうが、彼は2つのバブルでは生き延びた人物です。それは「ITバブル」と「住宅バブル」です。2つとも、グリーンスパンが作り出したバブルです。それが実はアメリカ経済というのは、ある意味では非常に大きな成長を遂げたし、またそのマイナス面も作り出してしまいました。これに対してグリーンスパンは辞める直前に、住宅バブルという言葉は使っていませんが、住宅価格高騰しているということに警鐘を鳴らしています。このまま行ったら将来アメリカ経済にとって非常に大きな問題が起こるかもしれないと警鐘を鳴らしています。
ではどうして住宅バブルがはじけたら大変な問題になるのか。もちろん日本も住宅バブルがはじけて大変な問題になりましたが、実はアメリカの景気を支えているのは個人消費です。個人消費を支えているのは住宅価格の上昇です。低金利と住宅価格の上昇なのです。もっと言うと、まずアメリカでは住宅ローンの借り替えが非常に簡単に出来ます。金利が下がるとみんなどんどん安いローンに切り替えて行くのです。それだけで返済負担が軽減し、可処分所得が増えます。もう1つはホームイクイティローンです。イクイティとは住宅の価値ですが、住宅を担保に借入を行うことです。住宅の価格が上がると担保価値が上がりますから、どんどん借入が出来ます。借入が消費を支える効果を果たしたのです。2005年半ばにアメリカの貯蓄率はマイナスになっています。通常の状況では所得の一部を貯蓄します。可処分所得の5%、10%、発展途上国は20%というところもありますが、率は別にしても所得の中から貯蓄が行なわれます。ところがアメリカの個人貯蓄はマイナスになっています。貯金をするのではなく、貯金を取り崩しているのです。どうして取り崩しているのかというと、住宅価格や株価が上昇し、資産が増えたからでし。もうこれ以上貯蓄を増やして資産を増やすことはないと感じているわけです。個人消費がアメリカのGDPの7割近くを占めていますから、個人消費を主導とした景気回復が続いているわけです。ここでもし住宅市場が崩れたら、マイナスの資産効果が働きます。そうなれば当然個人は貯蓄を増やします。
もう1つ非常に大きな問題なのは住宅ローンがかなり変動金利に移っていることです。利払いだけやって元本を払わないというローンも出て来ています。要するにローンを組んで元本と金利を返していくというのが普通の住宅ローンですが、金利を払うだで元本を返さない。どういうことかと言うと、将来これを売って住宅価格が上がるだろうから、売れば元本以上の売却益が出るわけですから、そこで元本を返す。その間は住宅ローンの金利さえ払っていればいいと、そういうローンもあります。その結果2000年から2005年までの間に、膨大な形の住宅ローンが積み上がっています。これが逆に金利が上がったり、住宅価格が下がったりすれば、個人消費は急激に落ち込むと思います。
2つ目は住宅ローン残高が膨大に膨れ上がった、この5年で倍ぐらいになっています。この大半は変動金利で、金利が上昇に転じれば多くの人が返済不能になりかねません。限界的なところで潜在需要を掘り起こしていく形で住宅ブームを作り上げてきたわけですから、反動も大きいでしょう。そこが崩れからアメリカの成長パターンが崩れて行くわけです。だから本当はグリーンスパンが狙ったのは、2004年から1月まで14回にわたって利上げした彼の本当の目的は何かと言うと、長期金利を少しずつ上げていって住宅過熱感を抑えたかったのです。ところが去年の夏ぐらいまで、長期金利はほとんど上がっていないのです。ですからイールドカーブが水平になっています。すなわち長期金利と短期金利がほぼ同じ水準になっています。普通だと期間と金利を取ると右上がりの曲線を描きます。期間が長いほど金利が高くなる。短期金利より長期金利が高い。ところが去年あたりからこれが横ばいで、長期金利と短期金利がほぼ同じ水準になっています。場合によっては短期金利の方が高くなっています。これは逆オールド曲線の状況が起こっています。
長期金利が上がらなかった理由というのは単純で、1つは外国から資本が大量に入って流入してきたからです。外国人のアメリカに対する債券投資、株式投資というのが膨大な量が入って来ていると。特に日本や中国の外貨準備の財務省証券購入は膨れ上がっています。大量のドル資金がアメリカに還流してきているのです。
これはバーナンキが言っている言葉ですが、今の世界は“貯蓄過剰”の状況にあります。彼はFRB理事としての最後演説で“グローバル・セービングス・グラッド”という言葉を使っています。世界は貯蓄が余っている。その余った貯蓄はどうしているかというと、全部アメリカに流れ込んでいて、それがドルの長期金利を下げているのです。そのことは同時にドル高の理由にもなっています。みんな絡んで来ているのです。去年の末ぐらいから長期金利、特に住宅金利が上がり始めています。だいたい2003年〜2005年ぐらいまで30年もので5%台だったのが、1月、2月6%台まで住宅金利が上がって来ています。場合によっては今年の末から来年にかけて7%ぐらいまで上がるかも知れません。そうすると住宅マーケットがうまい形でソフトランニングするのか、急速に冷え込むのかによって、アメリカの先行きというのは大きく変わっていくということです。しかしバーナンキは住宅マーケットに対する危機感を少なくとも公的な場では一度も喋っていません。マーケットのことはマーケットに任せろと言っているだけです。
もしマーケットで急速な調整が起こった場合、マクロ経済に対する大きな影響が出て来るのは避けられません。彼が住宅マーケットの過熱感を徐々に徐々に過熱感からソフトランニングさせるかどうかで、その手腕が問われることになるでしょう。住宅バブルを政策に組み込んで政策運営するかが、これからアメリカ経済に対する1つの大きなポイントになってくると思います。
第4四半期は1.6%、今年の第1四半期は5%〜5.5%を超える水準になると思います。結果的にはコンセンサスの見通しでは、今年は3.2%〜3.3%、FRBの予想もだいたいそれくらいです。去年が3.5%でしたから、ゆるやかに減速する感じです。これも前提条件としてはそういう印象に支えられた成長パターンは変わらない。その背後で支えている大きな住宅マーケットというのが崩れないというのが前提になっているわけです。
もう1つの前提というのは、これは非常に大きな要素です。為替マーケットがどうなるか。為替マーケットでドルがかなり過大評価されているというのは間違いないと思います。ですからこれをどういう形で調整を行うのか。この調整が資本流入に影響を与えてくれば、長期金利は思った以上に早く上がるかも知れません。ただアメリカの長期金利にとって幸いなのは、財政赤字の規模が少しずつ減り始めて来ていることです。大きな問題ではありますが。去年も当初予想ではアメリカの財政赤字は減る予定でした。ところがハリケーンが起こったので、結果的に財政赤字は増えてしまったわけですが、トレンドとしては減る方向に入って来ています。そういった意味では長期金利に対する影響というのは、若干緩和されるかも知れません。しかし逆に言うと資本流入そのものの状況はどうなるのか。それに絡んで為替マーケットの絡みが出て来るわけです。そのあたりは次の大きなポイントになって来ると思います。
ですから最初にバーナンキが試されるとすれば、最初に試されるのは為替市場でしょう。為替市場でドル高の調整が急速に起こるのかどうか。昨日発表された貿易収支は赤字が拡大しています。今のところ金利差だけでみんな動いています。要するにドル金利が高いですから、明らかに機関投資家はドルに運用した方がよっぽどいいわけです。キャリートレードと言って、日本のようなほとんどゼロ金利でお金を借りて、ドルで運用すると儲かるわけです。そういった意味で資本がアメリカに流れていますが、ここで日本の長期金利が上がるとか、ユーロの金利が上がるとか、金利差が下がった時に資金の流れが変わって来るかも知れません。そうするとこの7年間を支えて来た低金利、資本のアメリカ流入、それをベースにした長期金利の低下、住宅ブーム、そういった構造事態がどこかで変わってくる可能性があります。そのリスクをバーナンキは最初に背負っているのではないかと言うことです。
話が取り止めもなくなりました。ちょっと分かりにくいところも含めて何かご質問があれば。
質問 今、大幅に路線を変更しようとしている時にインフレターゲット論が出たり入ったりしていますが、そのへんはいかがお考えでしょうか。
中岡 90年台の後半ぐらいからインフレターゲット論というのは、学会の主流的な考え方になって来ています。海外の経済学者と一部の日本の経済学者というのが盛んにそれを主張した時期がありましたが、日本銀行はほとんど相手にしませんでした。日本銀行の中でも若干検討したみたいですが、それを与するという発想は全くなかったみたいです。私の知っている日銀の内部の方でも、インフレターゲットは聞くだけでも歯牙にもかけないような態度を取っておられました。それがここに来てバーナンキが議長になったものですから現金なもので、少しは対応しなきゃいけないのかなという雰囲気が出てきていますが、論理的には日銀のエコノミストには支持する人は少ないのではないようです。ただし妙な話なのは、自民党の政治家の方の中からそういう人達が出て来ていることです。ただその政治家の人達というのは何も理解していないのではないかと思います。要するに日銀に対してプレッシャーをかけるというような形で主張されているだけです。
インフレターゲット論のエッセンスというのは、ターゲットを掲げるということは、大きな中の1つにすぎません。インフレターゲット論というのは、中央銀行の政策の透明性を高め、政策に対するコミットメントを維持していくかであって、2%、3%という具体的な水準の問題ではないわけです。何%が合理性か判断はできません。大事なのは、どのようにして中央銀行の政策の透明性をどう高めていくのかが、議論の中心でなければならないということです。ところが、今の議論は何%にするかという議論が先行している気がします。日本銀行でどういう議論をしたのか、日本銀行の中で議事録を出しなさいとか、どういう政策意図があるのですかなどディスクローしなければいけない。そういう議論がすっぽり落ちているわけです。
だから今の日本のインフレターゲット論の議論の仕方は、マスコミも問題があると思いますが、数字だけの議論になっています。それはちょっと違うのではないかという気がします。
質問 今日はありがとうございます。1つ教えていただきたいのは、日本の識者の中にアメリカの国債を相当買っているという、売れないから話題にもなりませんが、双子の赤字じゃないですが、日本の財政は沈没寸前まで来ている。GDPの2年分を累積赤字として持っている。公共投資は減ったが、金利利払いだけで国家予算の3分の1が費やされてしまっている。でも意外とそれが安心できるのは、その額の半分がアメリカの国債で賄われている。言うなれば日本の赤字はアメリカの国債をいっぱい買っているから、最近は中国が盛んに買っているようですが、差引の赤字になっているけれども、そういう構造になっているという説明をする方がいますが、そこはどんな構造になっているのでしょうか。
中岡 その議論はまず基本的に間違っていると思いますね。要するに日本の財政赤字の問題と、例えば日本が外貨準備としてドルを持っているかというのは関係ない話です。変動相場制に移る時に本来なら外貨準備なんか必要ないということでした。為替相場は市場が決めるわけですから。日本の外貨準備が増えているのは、市場に介入してドルを買っているからです。市場に介入する時に円を売ってドルを買います。円資金は短期国債を出して調達しています。外為特別会計を通して処理されます。国内の財政収支の話とは全然違うわけです。ですからバランスシートで考えれば、外貨準備の反対側には円の債務があるわけです。外貨を持っているというのは別にその相方としての円の債務を持っているわけですから、本当に意味での日本の資産でもなんでもないわけです。中国も同じです。元を買い支えるために元を売ってドルを買っているわけです。今ドルを買いますね、ドルをキャッシュで持っていても利子が付かないですから、みんな財務省の短期証券か中期かどちらかを運用しています。それと今アメリカのドル金利は3%か4%ぐらいです。そうすると利子が入って来るわけです。ですから外貨準備がどんどん増えてくるわけです。ドルを買うためには円をどこかで調達しているわけですから、それで短期の国債を出しているわけです。
単純な話で、貿易で商社がドルを売りますよね。Aという商社がドルを売る。仮にBという商社が買えば、為替の売買は成立するわけです。しかしそれに対して中央銀行が買うわけですから、その分だけAという商社は円資金が増えます。そのまま置いておいたら銀行のマネーサプライが増えて来るわけです。そのマネーサプライが増えて来た時に、普通の金融政策はというのは、吸収する時には日本銀行は逆に債券を売ってキャッシュを回収するということです。こういうことをやるのを不胎化政策と言って、為替操作による国内の影響を遮断する方向があるわけです。放っておいたらマネーサプライが増えていきますから、景気刺激的になります。これは財政の黒字と赤字と全く違う話です。日本銀行が介入するためには財務省は資金を調達しなきゃいけないわけです。税金を使っているわけではないです。それの方法としては日銀引受で国債を出すわけです。国債の日銀引受はいけないのですが、外為証券は可能です。
質問 中央銀行と政府、財政当局との関係ですが、アメリカにおける中央銀行の存在というのは独立性を保ってFOMCの決定に参画されていて、世界をドル経済が支配しているということからそうなのかも知れません。それに対して日本の中央銀行と政府という関係は、福井さんがなろうと誰がなろうとあまり、一応独立性は言われていますが、代わり映えしないような感じですが、あるべき姿と申しますか、そのへんにつきましてお話いただければと思います。
中岡 日本銀行の金融政策決定会合というのがあります。ちょうどFOMCに対応しているような、1つだけ決定的な違いがあると思います、日本とアメリカ。日本の金融政策決定会合にはスタッフとして財務省の人が出て来ます。ですからほとんどのニュースのリークというのは財務省からです。ところがFOMCには財務省のスタッフは誰も出ていません。これは絶対と言ってもいい。もう1つはFRBの議長が財務省を訪れることはプライベートも公式にも絶対にないです。東洋経済というのは日銀の隣にありますが、よく言われたのは日本銀行というのは、昔、大蔵省の日本橋支店だと言われたことがあって、ほとんど独立性がなかった。人事も全部含めて完全に。アメリカでは理事は議会の承認を得る必要がありますが、いったん理事になったら独立性は保障されます。
日本の場合はほとんど財務省の影響下におかれていたので、新日銀法が出来て初めてなんとかしようとなったのです。それがまたいろんな弊害を起こしてきたわけです。例えば90年代末以降の金融政策というのは、どちらかと言うと日銀が独立性ということを固持するためにとってきた政策も結構あるわけです。結果的にはそれは失敗して、政府の介入を招くような事態を引き起こしているわけです。アメリカは非常に長い歴史の中で独立性を勝ちうるための、財務省とFRBの合意と言いましたが、金融政策の自由度、独立性を保つためにずっと闘っています。現実にいろんな総裁と議長と、財務長官の対立はたくさんあります。日本だと例えば小泉さんはこんなことを言ってはいけないのですが、上げちゃいけないとか。アメリカの大統領と絶対そんなことは言わないですよ。ただ問題なのは日銀がそれだけの信頼性を持ち得るかどうかということです。
この投稿には、まだコメントが付いていません
このコメントのRSS
この投稿へのトラックバック URI
http://www.redcruise.com/nakaoka/wp-trackback.php?p=175
現在、コメントフォームは閉鎖中です。