政治学者フランシス・フクヤマとネオコン:フクヤマのネオコン批判の論理
本ブログは『中央公論』6月号に掲載した「ネオコンに挑戦状を突きつけたフランシス・フクヤマ」の転載ですが、オリジナル原稿です。『中央公論』では11ページと長い論文でしたが、当初の執筆原稿を400字詰め原稿用紙で約5枚ほど削除したものです。編集後の論文のほうが歯切れは良いですが、面白い情報を幾つか削らなければなりませんでした。このブログは、削除部分を含んだものです。フランシス・フクヤマがネオコンを代表する論者であったというのは、多くの日本人には意外だったようです。本論文では、なぜ彼がネオコンを代表する論者と見なされたのか、その個人的な背景、思想的な背景を分析しました。しかし、彼がイラク戦争を契機にウィリアム・クリストルなどのイラク戦争強硬派のネオコンと袂を分かちます。本論文では、ネオコンを代表する評論家チャールズ・クラウサマーとの論争と3月発売のフクヤマの新著「America at the Crossroads」をベースに分析を加えてものです。それと同時に、本論文はアメリカの外交政策を巡る最近の論争を知るうえでも役に立つと思います。
アメリカ保守主義の復興の祖の一人であるリチャード・ウィーバーが1948年に書いた本『アイデズ・ハブ・コンスクエンス』は、アメリカ保守主義運動の思想的基盤を与えた書である。その「思想こそが結果をもたらす」という考えが、その後の保守主義運動を見事に説明している。70年代から顕著になってきたアメリカの保守主義運動は、81年のレーガン政権の誕生でピークを迎えた。アメリカの保守主義は伝統的な価値を重視する「伝統主義者」と経済的な自由を主張する「リバタリアン」を軸に発展してきたが、80年代以降、新たに「ネオコンサーバティブ」が台頭した。このインテリ集団で理論武装された少数のグループが、やがて保守主義運動を乗っ取り、アメリカの政治と外交を大きく変えていくことになる。
レーガン政権は、力の均衡をベースに東西のデタント(共存)を主張するキッシンジャーに代表されるアメリカ外交を根底から変えてしまった。レーガン大統領は、ソビエトを“悪の帝国”と呼び、東西対決を“善と悪”との戦いであると特徴つけた。2001年に成立したブッシュ政権は、レーガン政権と同様に一部の国を“悪の枢軸”と呼び、再び外交政策に道徳問題を持ち込んだ。レーガン政権の外交政策の背後にはネオコンといわれる人々がいた。そしてまた、ブッシュ政権の外交戦略策定の背後には、同じネオコンといわれる人々の存在がある。さらに、リベラル民主主義を世界に布教するというメシア的使命感を抱くネオコンは、「一国主義」と「先制攻撃」を主張する“ブッシュ・ドクトリン”の中で具体化され、イラク戦争を支える理論を提供することになった。
ネオコンの理念を実現するはずであったイラク戦争の3周年を迎えたアメリカは、今、その戦争の意味を巡って苦悩している。戦争を始める最大の根拠であったイラクが大量破壊兵器を持っているという主張は誤りであることが明確となった現在、ブッシュ政権もイラク戦争支持者たちも、今までのように声高に“道徳と正義”を主張できなくなっている。そのうえ、イラクの民主化の目処は立たず、イラク国内は内戦状況を呈するまでに混乱し、悲惨な状況を呈している。第二次世界大戦で連合国軍がパリに入城したときのように、バグダッドの市民に花束と歓声によってアメリカ軍が迎えられるというネオコンの夢は夢想に終わり、いまや悪夢にさえなろうとしている。保守派の内部からも保守派の重鎮ウィリアム・バックリーでさえ「アメリカはイラク戦争の負けを認める時である」とさえ主張している。
イラク戦争の状況は、当然のことながら、それを論理的に支えてきたネオコンの論理に対する懐疑も生み出している。現在、アメリカでは外交政策を巡る論争は、混迷と混乱の様相を呈している。そんな状況の中でネオコンに真正面から挑戦する本『岐路に立つアメリカ』(America at the crossroads)が3月に出版され、大きな波紋を呼んでいる。しかも、著者がネオコンを代表する論者であるだけでなく、『ニューヨーク・タイムズ』紙の書評欄で評者が「考え方が最も創造的で、最も面白く、また最も野心的な人物」と紹介するほど政治学者フランシス・フクヤマであることが、その波紋をいっそう大きなものにしている。ネオコンは、イラク戦争での厳しい現実だけでなく、思想の面においても深刻な挑戦を受けているのである。
フクヤマが世の中の脚光を浴びるようになったのは、『ナショナル・インタレスト』誌(89年夏号)に「歴史の終焉」と題する論文を寄稿してからである。この論文、88年にシカゴ大学に招かれて行った特別講義を元に書かれたものである。彼は、その論文の中でヘーゲルとマルクスの論理を援用しながら、歴史は近代化に向かって進み、最終的に「リベラル民主主義が共産主義に勝利する」ことで歴史の進化は終焉すると書いた。その年の11月にベルリンの壁が崩れたことで、彼の論文は一気に注目を浴びた。
フクヤマは、2006年版の『歴史の終焉』の「あとがき」に「多くの人は“歴史の終焉”とは単に思想と価値の領域だけの事柄ではなく、国益に沿って世界の秩序を形成するために実際にパワーを行使してアメリカが他の国に対してヘゲモニーを確立することを意味すると受け取った」と書いている。さらに「本のテーマは体制の問題ではなく、近代化の問題である」にもかかわらず、多くの読者は趣旨を誤解していると語っている。要するに、近代化のプロセスで体制が変化していくことが理論のポイントであるにもかかわらず、体制間の争いでリベラル民主主義が勝利する、すなわち資本主義が勝利すると理解したのである。だが、フクヤマの意図を超えて、この本は多くの人に影響を与えたのである。
そのフクヤマは、実はネオコンを代表する論者の一人なのである。ネオコンの定義付けは曖昧であるが、フクヤマは自らをネオコンと呼び、また世間も彼をネオコンの代表的な論者だと見ている。その彼が、真正面からネオコンが主張してきたイラク戦争を否定し、その論理に挑んできたのである。フクヤマのネオコン批判は、同じネオコンを代表する有力な論者の一人であるチャールズ・クラウサマーとの激しい論争を通して展開され、『岐路に立つアメリカ』の出版で頂点に達したのである。
フクヤマの経歴とネオコンとの関係
「フクヤマ・クラウサマー論争」を分析する前に、なぜフクヤマがネオコンの代表的な論者になったのかを、彼の経歴をたどりながら見ておこう。
彼は52年にシカゴに生まれている。フクヤマの父ヨシオはロサンゼルス生まれの日系アメリカ人、母トシコは、戦後間もない49年にアメリカに留学し、ヨシオと出会い、結婚することになる。フクヤマが生まれたとき、父はまだシカゴ大学で宗教社会学を学ぶ学生であった。彼は後にピューリタンの一派である会衆派教会牧師になる。母は陶芸家である。会衆派教会は直接民主主義や奴隷制廃止を主張するなど伝統的にリベラルな宗派で、フクヤマが右派のシンクタンクであるランド・コーポレーションに勤務し、保守派のレーガン政権のもとで働くことを必ずしも快く思っていなかったという。
フクヤマは、74年にコーネル大学に入学して、古典を専攻する。同大学に在学中に後にブッシュ政権で国防副長官に就任し、イラク戦争を積極的に推し進めた有力なネオコンの一人であるポール・ウオルフォウィッツと運命的な出会いをする。学部の学生のとき、彼は成績優秀な学生だけが住むグループハウスに住んでいた。ウオルフォウィッツは、ハウスの理事会の理事の一人で、エール大学の政治学教授であった。その後、エール大学大学院に進んだフクヤマは、政府の政府軍管理・軍縮局に移っていたウフォルオウィッツのもとでインターンを経験している。彼との出会いがフクヤマにとって思想面だけでなく、将来のキャリアにとっても重要な出会いになるのである。
ウオルフォウィッツがフクヤマにネオコンの影響を与えた最初の人物だとすれば、二人目は彼がハーバード大学大学院に転校して師事したアラン・ブルーム教授であろう。彼はアメリカ社会の文化と教育の危機を論じた『アメリカン・マインドの終焉』を著し、有力なネオコン論者としても知られていた。フクヤマは、ブルーム教授からプラトンやネオコンに大きな思想的影響を与えたレオ・ストラウスの政治哲学について学ぶことになる。その影響から、フクヤマは自ら「自分はアラン・ブルームの学生である」と語っている。「歴史の終焉」を執筆するきっかけとなったシカゴ大学での特別講義も、ブルームの手配によるものであった。ちなみに、ハーバード大学時代の同級生にウィリアム・クリストルがいる。彼はネオコン創始者といわれるアービング・クリストルの息子で、大学卒業後、ブッシュ政権(父)のダン・クエール副大統領の首席補佐官を務め、その後、ネオコンの機関誌ともいえる週刊誌『ウィークリー・スタンダード』を創刊することになるネオコンの中心的な人物である。
大学卒業後、ランド・コーポレーションに就職したフクヤマは、さらに彼に大きな影響を与える人物に巡り会う。核戦略の専門家で、核拡散防止を積極的に主張したアルバート・ホールスセッターである。彼は64年から80年までシカゴ大学政治学部で教鞭を取っており、その時の学生にウオルフォウィッツや、レーガン政権のときに国防次官で対ソ強攻策から“ダーク・プリンス”と呼ばれ、またイラク戦争も積極的に支持したリチャード・パールなどがいた。フクヤマとウオルフォウィッツは、ホールスセッターという共通の師を通してもつながっていたのである。
フクヤマは、ウオルフォウィッツに誘われて81年から82年に政策立案スタッフとして国務省に勤務している。その後、パレスチナ自治区を巡るエジプト・イスラエル会談にアメリカ代表団に加わったりしているが、政府の要職に就くことはなかった。ウオルフォウィッツは94年にジョーンズ・ホプキンス大学の大学院SAIS学部長に就任したとき、ジョージ・メイソン大学で教えていたフクヤマを同校の教授として迎え、現在もフクヤマは同大学の教授の座にある。
フクヤマが明確にネオコンの旗幟を鮮明にするのは、90年代に入ってからである。クリントン政権が成立したことで、ブッシュ政権(父)で要職にいたネオコンたちは野に下り、クリントン政権に対抗する政策立案にかかわっていく。そして、リチャード・チェイニー(現副大統領)やドナルド・ラムズフェルド(現国防長官)、ウオルフォウィッツなどの有力者をスポンサーにシンクタンク「新アメリカ世紀プロジェクト」が設立され、フクヤマもディレクター招かれる。このシンクタンクが、90年代のネオコンの活動拠点になり、冷戦後のアメリカの外交政策を検討し、ブッシュ政権が誕生すると、その多くが実際の政策として採用されていくことになる。
同プロジェクトは、97年6月にクリントン大統領宛に書簡を送り、外交政策の提言を行っている。この書簡は25名の連名で書かれ、その中にフクヤマの名前もあった。この書簡は、ネオコンの外交政策の基本の表明でもあった。同書簡は、冷戦後、アメリカが世界の唯一の超大国であると謳いあげ、「海外で政治的、経済的自由を推進する必要がある」と主張している。ここに既にネオコンのメシア的使命感が伺われる。
翌98年に再び同プロジェクトはクリントン大統領宛に書簡を送り、「サダム・フセインを権力の座から排除する」ことを求めたのである。さらに書簡の中で「アメリカの政策は国連安全保障理事会の全会一致という間違った方針によってこれ以上阻害され続けるわけにはいかない」と、国連への不信を露骨に表現している。フクヤマは、この書簡に署名した18名のうちの一人である。こうした活動を通して、フクヤマは、90年代末にはネオコンの中核的な存在になっていた。
フクヤマとクラウサマー論争の始まり
だが、フクヤマは次第にネオコンの主張に違和感を覚え始める。02年4月に新アメリカ世紀プロジェクトがブッシュ大統領にイスラエル政府を強力に支持することを求めた書簡にフクヤマの署名はない。ネオコンの中心的人物の多くはユダヤ人であり、彼らのイスラエルに対する姿勢にフクヤマは次第に批判的になっていた。それは、後述するクラウサマーとの論争の中にも顔を出している。フクヤマは、クリントン大統領宛の書簡でサダム・フセインの排除を主張したが、「その時点でイラク侵攻のカードは入っていなかった」と述べ、自分はイラク戦争を支持していたわけではないと弁明している。03年3月のアメリカ軍のイラク侵攻で、フクヤマはネオコンの主張に同調できなくなる。彼は、アメリカのテロに対する過剰反応を懸念していたのである。
イラク戦争が始まる前の03年1月のある土曜日、バージニア州アーリントンにある表札も出ていないビルの一室で国防総省ネット・アセスメント部の会合が開かれた。同部は四つの専門家グループに国際的なテロの長期的な脅威について分析を依頼していた。その日、各グループが分析結果を報告するために会合がもたれた。フクヤマは、四つのグループのうちの一つのグループの責任者であった。ウオルフォウィッツ国防副長官は、四つのグループのうちフクヤマが責任者を務めるグループのプレゼンテーションにだけ顔を出した。その席でフクヤマは、「アメリカは9月11日のテロに過剰反応すべきではない」と報告し、特に軍事行動を取ることに慎重な対応を求めた。おそらく、その分析は、彼のメンターであるウオルフォウィッツを失望させたであろう。
04年の夏、フクヤマは欧州に滞在していた。バイオテクに関する本『ポストヒューマン・フューチャー』を執筆するのが目的であったが、そこで欧州の知識人やジャーナリストと議論する機会を得た。イラク戦争を始めるにあたって、クリストルやロバート・ケーガンといったネオコンは同盟関係を軽視し、アメリカが単独で軍事行動を取ることを主張し、国際協調を主張するフランス、ドイツとの間には深刻な亀裂が生じていた。
後日、フクヤマは「(欧州滞在中の)このときから私はアメリカのヘゲモニー問題全体を考えなおし始めた」と述懐している。そして「その時までは私は、アメリカは覇権国であるが、慈愛に満ちた覇権国であるというネオコンの主張を受けいれていた」と、ネオコンの思想に本格的な懐疑を抱き始めたことを認めている。
フクヤマのネオコン批判を決定的にしたのが、04年2月にワシントンのヒルトンホテルで行われたアービング・クリストルを記念する晩餐会でのチャールズ・クラウサマーの「民主的現実主義-一極世界におけるアメリカ外交」と題するスピーチであった。クラウサマーがスピーチの中でイラク戦争を“実質的に完全な勝利”と主張し、会場にいた多くの人々がそのスピーチに喝采する様を目の当たりにしたフクヤマは当惑する。翌日、『ナショナル・インタレスト』誌のジョン・オサリバン編集長に会った彼は、クラウサマーのスピーチに対する反論を書かせてくれるように頼んだ。オサリバンは即座に了承し、同誌の04年夏号に「ネオコンサーバティブ・モーメント」と題するフクヤマの論文が掲載された。これが、フクヤマが公然とネオコンに向けて放った最初の批判の矢であった。
ネオコンの正当性を主張するクラウサマー
フクヤマの批判の対象となったクラウサマーは50年3月にニューヨクで生まれのユダヤ人である。ハーバード大学医学部を卒業し、ボストンの病院で精神科医として働いていたが、医者を辞めてリベラル派の雑誌『ニュー・リパブリック』に寄稿を始める。80年には大統領選挙でモンデール民主党候補のスピーチライターを務めている。87年に優れたエッセイを書いたとしてピューリッツア賞を受賞するなど、一流のジャーナリストである。彼は、リベラル派の雑誌に寄稿するだけでなく、保守派の雑誌にも積極的に寄稿するなど幅広い立場を維持している。『ワシントン・ポスト』紙のコラムニストとしても人気がある。
彼はリベラルなバックグラウンドも持っているが、その主張は強硬なネオコンである。サダム・フセインの排除を主張した01年9月20日の新アメリカ世紀プロジェクトがブッシュ大統領へ宛てた書簡に初めて署名者として登場している。フクヤマからすれば、批判の対象のネオコンとしては申し分ない相手であった。
では、クラウサマーは「民主的現実主義」の中で何を主張したのであろうか。まず、彼は、ソ連の崩壊後、一つの超大国(すなわちアメリカ)が世界を支配する世界が出来上がったと分析する。ローマ帝国以来、こうした一極世界が登場したのは初めてであり、そうした世界でアメリカの外交はどうあるべきかと問いかける。そして、アメリカ外交を三つの流れに特徴つける。まず、「孤立主義」であるが、「これは現代の世界にはまったく通用しない」と退ける。二つ目は「リベラルな国際主義」で、これはウィルソン大統領のユートピア主義に起源があり、90年代のクリントン政権の政策であったと分析する。「リベラルな国際主義」の外交政策は、人道的介入、多国籍主義、道徳的説得を柱とする。クリントン政権はソマリア、ハイチなどに介入したが、そうした人道的介入には「国益」という視点が欠けていたと批判する。また、多国籍主義も、アメリカのパワーの行使を制約するために利用されているに過ぎないと主張する。道徳的説得も、独裁者に政策変更を迫ることはできないと、これも外交政策の柱としては不十分であると指摘する。
三つ目の「現実主義」は、力の均衡を外交の柱とするキッシンジャーに代表される外交政策で、共和党主流派や外交の専門家の多くが支持する外交政策である。現実主義者は「一極世界では秩序はアメリカの圧倒的な力と抑止力によって守られている」と考え、必要であれば一国主義や先制攻撃も辞さないと主張する。しかし、クラウサマーは、パワーだけでは有効な外交政策は行えないと現実主義の限界を指摘する。なぜなら「現実主義にはビジョンがないからである」。手段はあるが、目的がないため外交の使命を明確に規定できないというのがクラウサマーの批判のポイントであった。
現実主義の外交政策は、キッシンジャーのデタント政策に見られるように、単なる力の均衡に基づく政策であり、そこには“体制”に関する視点はまったく見られない。要するに、現実主義者は対峙する国の体制の内容は問題にしないのである。要するに、ソビエト体制は永遠に続くと考えて、体制の変更を図るよりも、異なった体制の共存を図ろうとするのが現実主義の外交政策である。これは、リベラル民主主義の普及がアメリカ外交の基本であると考え、外交政策の中に「レジーム・チェンジ」を掲げるネオコンとは基本的に異なった発想である。ちなみに、政治における体制の重要性を指摘したのは、ネオコンの思想に大きな影響を与えたストラウスであった。そのことが、ストラウスがネオコン思想の祖の一人とみなされる理由である。
クラウサマーは、現実主義の外交政策に“道徳”を持ち込んだのはレーガン大統領の功績であったと指摘する。すなわち、レーガン大統領は、米ソの対立を「自由と不自由の戦い」「善と悪の戦い」に変えた。民主主義の普及を説くネオコンがレーガン大統領に親近感を抱くは、このためである。
ビジョンに欠ける現実主義に改良を加えたのが、四番目の外交政策の「民主的グローバリズム」である。これは「国益をパワーによってではなく“価値”によって規定する外交政策」である。クラウサマーは、アメリカにとって価値とは「自由の普及」であり、それこそがアメリカの使命であると主張する。ただ、同じ世界への民主主義の普及を主張するウィルソン主義と「民主的グローバリズム」の決定的な違いは、国際機関を通して民主主義を普及させようとするのか、それとも超大国としての責任を果たすために一国主義での行動も辞さないとするかにある。
しかし、「民主的グローバリズム」は、「普遍主義に偏り、過剰に自由にコミットし、世界の至るところに民主主義の旗を立てようとする誘惑に駆られる危険性」を持つ。したがって、クラウサマーは、「民主的グローバリズム」をもっと狭く自己規制した「民主的現実主義」こそ、アメリカの取るべき外交政策であると主張する。すなわち、戦略的に必要な場所、“生存にかかわるべき脅威”が存在する所で民主主義を実現する戦いを行う必要があると説く。世界のどこででも構わないからリベラル民主主義を実現させればいいというわけではないのである。クラウサマーは、そうした生存の脅威が存在する場所はアラブ・イスラムであるという。さらに、アラブ・イスラムを脅威と規定する背景には、サミュエル・ハンチントンの「文明の衝突」的な世界理解と、ジハードを掲げるイスラム過激派のテロがあった。
フクヤマのクラウサマー批判
フクヤマは、『ナショナル・タレスト』に掲載した論文「ネオコンサーバティブ・モーメント」でクラウサマーの批判を試みる。その批判を受けて、クラウスサマーは同誌の04年冬号で「民主的現実主義を擁護する」と題する論文でフクヤマに対する反論を行っている。その中でフクヤマが、ネオコンは外交政策をイスラエル化していると書いたことから、クラウスサマーが“反ユダヤ主義的”であると厳しい批判をフクヤマに加えている。また、なぜイラク戦争が始まるときに沈黙を守り、今になって声高に批判するのかとフクヤマに迫る文章もあった。これに対してフクヤマは、「世論が完全にイラク戦争支持に傾いているとき、自分が発言しても人は聞く耳をもたなかったろう」と答えている。いずれにせよ、その後、お互いに「相手に答える」短い論文を何度か掲載し、熾烈な極め論争は続いた。これを境に二人は口をきくこともなくなった。
一時、論争は収まったかに見えたが、フクヤマは06年2月19日付けの『ニューヨーク・タイムズ』紙に「アフター・ネオコンサーバティズム」と題する長い論文を寄稿し、再びネオコン批判を展開する。さらに、『岐路に立つアメリカ』が出版されたことで、それまで小出しであったフクヤマの思想の全貌が明らかになる。この本は05年にフクヤマが行ったエール大学での集中講義をもとに書かれたものである。フクヤマと両者の議論を逐一比較検討すると面白いが、それだけの紙幅に余裕はない。それぞれの論文には重複している部分もあり、以下では『岐路に立つアメリカ』での議論をベースに、フクヤマの主張を整理してみる。
フクヤマのネオコン批判は、大きく分けて「アメリカの軍事行動の合法性」「イスラム社会を生存にかかわる脅威と判断すべきかどうか」「イラクの戦後復興と安全保障に対するネオコンの計画の杜撰さ」に要約できる。合法性の問題は「一国主義」と「多角主義」の問題に絡んでくる。フクヤマは「ネオコンは合法性は行動の後から国際社会なら与えられるものであると考えている」と批判している。しかし、ブッシュ政権は、イラク戦争の根拠の一つであった大量破壊兵器の存在を証明できなかったために、“事後的”にもアメリカは国際社会から合法性を与えられていないと主張している。
フクヤマは、外交政策思想を「孤立主義」「現実主義」「リベラル国際主義」に「ジャクソニアン・ナショナリズム」を加えて、四つのカテゴリーに分類している。それらの外交政策思想に検討を加え、最終的にクラウスサマーの「民主的現実主義」という概念に対抗して「現実的ウィルソン主義」という概念を提唱する。それは「民主的現実主義」が力の均衡を主張する現実主義とネオコンのメシア的使命と一国主義の外交政策を一体化させたのに対して、「現実的ウィルソン主義」は現実主義とウィルソン主義を一体化させたものである。要するに、アメリカ外交が道徳的な目的を持つべきであるという点でウィルソン主義的であるが、その政策実施に際して過剰な楽観論を排するという意味で現実主義であるという。
さらに「現実的ウィルソン主義」は、一国主義ではなく、国際機関を尊重する多国籍主義の立場を取るという意味でウィルソン主義的である。しかし、国の体制の問題を重視するという点ではネオコン的であるが、現実主義と一線を画している。フクヤマもネオコンも、アメリカの外交は道徳的使命を果たすべきだと考える点ではまったく同じである。道徳的使命を失ってしまえば、アメリカの理念に反すると考える点では、両者に基本的な差はない。ただ、それを実現する手段で両者は袂を分かつのである。ネオコンは、一極世界ではアメリカは唯一の大国であり、世界の安全保障を維持する責任があると考える。こうしたアメリカは特殊な使命を持っているという考え方は、アメリカの伝統的な考え方で、「アメリカ例外主義」と呼ばれる。
フクヤマは、外交政策の中に道徳的な目的を含めることには賛成しつつも、「アメリカは自分の善意を信じているだけでは駄目で、アメリカ人以外も納得させなければならない」と主張する。そのためにも、国際機関を尊重しなければならない。フクヤマの「現実的ウィルソン主義」は、ウィルソン主義的ユートピアではなく、現実主義者の視点を踏まえながら、国際機関を通した国際協調を外交の柱にすることを提唱しているのである。
またイスラム過激派についても、フクヤマは、脅威を過大に評価すべきではなく、アメリカは世界でせいぜい数千のアメリカに損害を与えているイスラム過激派と戦っているのであって、イスラム世界全体と戦っているのではないと主張する。こうした過激派は「文化の衝突」から生まれたのではなく、近代化、国際化の副産物として登場したのであり、彼らは自らの使命を実現する力は持たないと分析する。そのためアメリカの政策は、軍事力を行使するのではなく、普通のイスラムの人々の心に訴えるべきだと主張している。
レジーム・チェンジと国家建設
では、オコンはイラン戦争でなぜ間違を犯してしまったのだろうか。フクヤマは、それを理解するためには冷戦勝利まで遡らなければならないという。冷戦の頃は、ネオコンはアメリカの保守主義グループの中できわめて少数派でしかなかった。レーガン政権は彼らの主張であるレジーム・チェンジを外交政策として採用することになる。そうした政策は、現実主義者や外交の専門家には無視されていた。しかし、結果的にレーガン政権の対ソ強攻策によってソビエト体制は崩壊し、ネオコンのレジーム・チェンジ政策は見事に無血で成功を収めたのである。すなわち、ソ連の“民主化”は成功したのである。
ネオコンは、ソビエト崩壊から幾つかの教訓を引き出した。まず、全体主義の国家は“最終的”に崩壊するというということである。しかも、ソビエト崩壊後、東欧では雪崩を打ったようにレジーム・チェンジが起こる。これが、ネオコンにレジーム・チェンジに対する自信を深めることになった。そして、ネオコンは、「イスラム世界でも同様なレジーム・チェンジがどうして不可能だといえるか」(クリストル)主張し始めたのである。イラクは生存にかかわる脅威であり、イスラム世界のレジーム・チェンジは可能であるとの過信が、ネオコンのイラク戦争を推進する論拠となった。
しかし、フクヤマは、イスラム社会のレジーム・チェンジについて次のように反論する。イスラムの特殊な社会構造はネオコンが想像する以上に複雑なものである。東欧の民主化はもともと民主主義のルーツを持っている社会であり、イスラムの世界とは基本的に異なっている。多くのネオコンは、そうした事実を無視して、楽観的なレジーム・チェンジの絵を描いたのである。その結果、ネオコンは、アメリカは自ら積極的に状況を変えていくことができるという“レーニン主義”に陥ったと批判する。
もう1つのポイントは国家建設である。フクヤマは、04年に『ステート・ビルディング』と題する本を出版している。フクヤマは、ネオコンは国家建設でも、伝統的なネオコンサーバティズムから逸脱したと指摘する。伝統的ネオコンは、ジョンソン大統領の「偉大な社会計画」を徹底的に批判した。そうした社会工学(ソーシャル・エンジニアリング)は、国家の過剰な介入を招き、予想したとは反対の結果を生み出す可能性があるからだ。だが、イラクでネオコンがやろうとしていることは、まさに社会工学的な国家建設であり、伝統的なネオコン思想に反するものではないかと批判する。フクヤマは、国内で上手くいかなかった社会工学的な国家建設がどうして上手くいくのかと疑問を呈す。しかも、1899年のフィリピン統合後、アメリカは一八カ国の国家建設に携わってきたが、ドイツ、日本、韓国以外はすべて失敗していると、国家建設の難しさを指摘している。
これに対して、ネオコンはどう反論しているのであろうか。クリストルは「イラクの国家建設は長期プロジェクトである」と反論する。現在、イラクが内戦状況になっているのは、民主化のプロセスとして避けがたいことであると主張する。さらに民主化や安全保障の確立が進まないのは、アメリカ政府が十分な軍事的、金銭的な資源を投入していないらであると、イラクの民主化と国家建設は可能であるという立場を崩していない。アメリカが十分な軍事的展開をしていないのは、ラムズフェルド国防長官に責任があるとして、同長官の辞任を求めている。
さらに、クリスタルを含めた三四名が、05年1月28日に議会に「アメリカ軍は私たちが求める責任を果たすにはあまりにも規模が小さすぎる」と主張し、軍の増強を求める公開書簡を送っている。彼らは、まだイラク戦争が負けたとは認めていないし、またアメリカ主導のもとに民主化、国家建設は可能だと考えているのである。クリストルは「アメリカ軍が長期にわたってイラクに駐在することが民主化にとってきわめて重要である」と、早期撤退計画を批判している。
フクヤマはネオコンと決裂したのか
では、フクヤマは、完全にネオコンと絶縁したのであろうか。彼は「20世紀の中葉から始まったネオコンサーバティズムは一貫性のある原理である」と、その思想性を高く評価している。それが90年代に政治によって利用され、歪められたとも述べている。「ブッシュ政権の外交政策の代名詞になってしまったネオコンサーバティズムという言葉を取り戻す努力は現時点では不毛である」と、厳しいコメントをしている。
彼は自ら『アメリカン・インタレスト』誌を創刊し、独自の活動を始めている。ネオコンサーバティブの祖の一人であるアービング・クリストルは『パブリック・インタレスト』と『ナショナル・インタレスト』という二つの雑誌を創刊し、ネオコン思想の普及に貢献した。『アメリカン・インタレスト』という誌名からすれば、フクヤマは伝統的ネオコンサーバティブに対する拘りは持ち続けているのかもしれない。ある論者は、「マルクス主義者がスターリンからマルクス思想を切り離すことで、その思想を救おうとしたように、フクヤマはブッシュ政権と一体化したネオコンからネオコン思想を切り離すことで、ネオコン思想を救おうとしているのかもしれない」と分析する。
フクヤマは「クラウスサマー批判はあなたの思想のパラダイムの転換を示しているのか」と聞かれたとき、「そのことがパラダイムの転換を促すことになるのかどうかわからない」と答えている。さらに、「ネオコンサーバティズムはテストに直面している。変化する現実に対応して調整するか、あるいは硬直的な原則に固執するか。その選択によって、ネオコンの時代は終わるか、生き残るかが決まるだろう」と述べている。
ブッシュ政権の中ではライス国務長官を中心に“ネオ現実主義”の動きが出ている。競合する外交思想の中で、どれが次のアメリカの新しい外交思想になるのであろうか。ネオコンの「民主的現実主義」なのか、フクヤマの「現実的ウィルソン主義」なのであろうか。思想は、現実によって試されることになるだろう。最初のウィーバーの言葉に戻ろう。「思想は結果を生む」ものである。言い換えれば、思想は結果によって判断されるのだろう。ネオコンサーバティズムは、まさに結果によって判断されようとしているのかもしれない。
1件のコメント
このコメントのRSS
この投稿へのトラックバック URI
http://www.redcruise.com/nakaoka/wp-trackback.php?p=176
現在、コメントフォームは閉鎖中です。
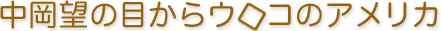



大変興味深く読ませていただきました。「国家の罠」の佐藤優氏はネオコンの思想的バックボーンについて「あなどれない」とインタビューで答えていました。自分としてはいいわるいは別にしてアメリカの知識人たちの真摯(そう思いたい)な結論の一つと考え、注目しています。最初にネオコンという言葉を知ったのは「ニューヨーク知識人」堀邦維著という本でした。30年代の共産主義者から80年代にネオコンに流れていったニューヨークのユダヤ知識人たちについて書かれており、政治主義はちがっても大衆恐怖症的でエリート主義と言う点で一貫しているという指摘がありました。本文中紹介されている「アメリカン・マインドの終焉」は読んだ当時、アメリカの知識人の真摯な言葉としてとても感銘しました。2001年にイェール大医学部に留学していたとき、医学部生同士で「君の読みたがっていた本だろう?」とクリスマスプレゼントに送っているのを見たとき、この国で読み継がれているのかなあと思いました。この作者アラン・ブルームがネオコンの父の一人、というより実際の政治に深くコミットしていたとは思ってもみませんでした。その後「ウルカヌスの群像」で、レオ・ストラトスーブルームーネオコンの線があきらかとなり、どこかにこの記事がのると必ず読むようになりました。わたしは、沖縄に住んでおりアメリカを無視した生活は考えられません。かつて「猫の許す範囲で遊ぶネズミ」と言われましたが、悔しいですが真実です。フランシス・フクヤマの今後の展開がとても気になります。
コメント by のは — 2006年6月21日 @ 10:57