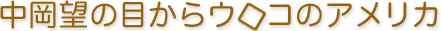「9月11日」の思い:連続テロ事件とアメリカ社会
幾つかの未完の連載があります。「ブッシュ・ドクトリンとネオコン」「アメリカ経済、80年代の再現かードル下落の背景」は、まだ続きを書かなければなりません。が、日々の仕事に追われ、なかなか時間が取れませんが、ちゃんと最後まで書きますのでご容赦を。今回は、2001年9月11日の連続テロ事件は、おそらくアメリカの社会と歴史を変えてしまったほどの衝撃をアメリカの人々に与えたのかも知れません。やや誇張があるのかもしれませんが、今でも多くのアメリカ人は拭いがたいトラウマに囚われているようです。今回は、私がセントルイスのワシントン大学にいたときに、キャンパスで行なわれた1周年の犠牲者を悼む会合に出席したときの印象をエッセイに綴ったものをアップします。テレビで報道されるアメリカとは違った姿が、そこにはあると思います。これも、やや長いエッセイですが、ぜひお読みください。続きは次の「more」をクリックすると読めます。
サイレンス:もう1つの追悼式
(セントルイス、ワシントン大学、クアド広場で。2002年9月11日夜)
この2週間、セントルイスでは快晴が続いている。8月の末に連日続いた激しい雷雨は本当だったのかと思わせるような雲1つない日が続いている。9月11日、いつもより早くアパートを出た。ドアを開けると、輝くような日差しが嘘のように爽やかな風が体を包んだ。大学まで歩いて10分、いつもより早足で歩いた。
夜になっても抜けるような青空は続いていた。もうとっくに太陽が落ちた午後7時、大学構内にあるクアッド広場の芝の上に座って空を見上げると、暗闇の中でも空は昼間よりも青さを増しているが、その存在が確認できた。昼間の爽快な風は、日が落ちると肌寒さを感じさせるようになっていた。半袖から出た二の腕を掌でこすらないと、寒いほどであった。
その追悼式はチャプレン(牧師)の話から始まった。説教というよりは、やはり「話」というべきだろう。聖書の句を引用するでもなく、人々の悲しみについて語り、暗殺されたケネディ大統領の言葉を引いて、人々の希望について話しをした。
チャプレンの話が終ると、ステージに座っている学生が演台の前に進み出て、話始めた。スピーカーから聞こえる声は、校舎に囲まれたクアド広場を巻き込むように響く。よく聞き取れない。「人種に関係なく、宗教に関係なく、ジェンダーに関係なく、社会的な地位に関係なく・・・・」と聞こえる。そして、彼に代わって中近東からの男女の学生が演壇に進み出た。訛りの強い英語で何かを話す。スピーカーの反響で聞き取れないので、ちょっと苛立ちを感じていたら、男女の学生は歌を歌い始めた。歌というのは間違いだろう。「コーラン」の賛美歌を歌い始めたのである。二人の声は素晴らしいハーモニーを奏でる。特に女性のソプラノの美しさは、その小さな体のどこからでてくるのだろうかと思うほど美しい。芝生に座った学生たちを優しく包み込む。神に対する祈りの賛歌である。
続いて演題に進み出たのが、やはり男女の学生であった。ヒンズー教について簡単に話始めた。ヒンズー教の神とは何か、平和とは何かについて簡単に説明した後、二人もヒンズー教の賛美歌を歌い始めた。悲しいほど美しい響きであった。それも神の賛歌であり、平和への願いの歌であった。
その後、一人の女子学生が演壇の前に立ち、話し始めたが、その甲高い声とスピーカーの反響で断片的にしか聞き取れなかった。彼女の話が終ると、先に演台で話をした学生たち10人くらい、揃ってステージを下りて行った。
その後、しばらく「レクイエム」がクアド広場に流れていた。ステージの椅子が取り除かれ、ステージの後方に雛壇が現れた。誰もいないステージ。芝生に座った学生たちは、誰一人私語を交わすことなく、じっとしている。「間が空きすぎているのでは」と思ったとき、約50人の学生が列を作ってステージに上がり、雛壇に位置した。それに続いて裾の広がった白い服を着た女子学生が8名、ステージにあがった。音のないなかで、数人が踊り始めた。創作舞踊のような踊りである。しばらくすると雛壇の学生たちが一斉に歌い始めた。それまでクアド広場を支配していた沈黙が一気に破れた。無機的に見えた踊りが命を得て、激しい踊りに変わった。踊りが10分くらい続いただろうか。芝生に座っている多くの学生は、ただ黙ってみているだけである。踊りが終ると、拍手が起こった。誰も「ブラボー」とは叫ばない。静かな、しかし暖かい拍手であった。
一人の中年の男性がステージの横に移されていた演台の前で、静かに話し始めた。最初は何か分からなかった。それは、詩の朗読であった。それが彼の創作の詩なのか、誰かが作った詩なのか分からない。スピーカーを通して、ゆっくりとした落ち着いた声がクアド広場を包む。
「サイレンス、ツナイト、スキェアーズ・ユー(Silence, tonight, scares you)」とゆっくりした口調で詩を読み上げ始めた。「今夜は、沈黙があなたたちを恐怖させる」。朗々とした透き通った声で朗読が続く。「沈黙に耳を傾けよ、3000名の苦しみのささやきが聞こえる」「沈黙に耳を傾けよ、かすかな呼吸と心臓の音が聞こえる」「沈黙に耳を傾けよ、そこに何かが起こりつつある。それは可能性だ」「沈黙に耳を傾けよ、もうあなたは一人ではない」・・・。その詩を聞きながら、メモ用紙を持ってこなかったことを悔いた。今、耳に残る音を断片的に思い出しながら書いている。
僕の隣に座っていた女子学生が、1本の蝋燭を渡してくれた。詩の朗読が終ると、一斉に蝋燭に火がつけられた。わずかであるが風が吹いており、僕の蝋燭になかなか火がつかない。すると側にいたすらりとして黒人学生が、あかあかと燃えている自分の蝋燭をもって近づいてきて、僕の蝋燭に火をつけてくれた。芯が焼けていたので、火がつくまで、かなりの時間がかかった。彼女は何も言わず、じっと自分の蝋燭の火を僕の蝋燭につけたまま立っていた。やっと僕の蝋燭に火がつき、僕か彼女だけに聞こえるように「サンキュー」といった。彼女は軽い笑顔をしただけで、元の自分の場所に戻った。
クアド広場にいる全員の蝋燭に火がついたことを確かめると、詩を朗読した男性は、「蝋燭の火を掲げて下さい」という。全員が立ち上がり、蝋燭の火をかざす。「周りを見回してください。もうあなたは一人ではないのです」。それだけいうと、ステージを下りていった。
残された学生は、しばらくその場に立ちつくしていた。誰ひとり、一言も発することなく。そして、一人、二人と火がついた蝋燭を手に、クアド広場から去っていく。ある学生はずっと蝋燭に火をつけたままであり、ある学生は火を消して、黙って去っていった。この間、1時間半。ステージで語り、踊った学生以外は、誰一人として一言も声を発しなかった。
7時に追悼式が始まったとき、まだ青い空が確認できたが、もう完全な暗闇になっていた。大学の門を通り、階段を下り、帰路についた。そのとき、どうしようもない感動が襲ってきた。これは、ワシントン大学で行われた9月11日のテロによる犠牲者の追悼式である。久しく、これほどの感動を感じたことはなかった。
半分燃えた蝋燭が、今、机の上に置かれている。
11日、目覚めたのが7時だった。セントルイスとニューヨークの間には時差が1時間ある。アメリカに来て以来、朝、起きると習慣的にCNNか、フォックス・テレビのニュース番組を見るようになっている。その日もテレビをつけると、すでにニューヨークの世界貿易センタービルの跡地で、追悼式が始まっていた。「グランド・ゼロ」と画面に出ている。
僕にとって、「グランド・ゼロ」という言葉は国防総省と結びついている。五角形の国防総省の建物の中は広場になっている。そこに1軒の喫茶店がある。その喫茶店のニックネームを「グランド・ゼロ・カフェ」という。国防総省の担当者に理由を聞いたら、「核戦争が起こったら、最初に国防総省が狙われるだろう。核が落ちれば、最初にグラウンド・ゼロになるのが、ここだからだ」という答えであった。その真偽は知らないが、納得できる説明であった。
そしていま、本当に地上に「グランド・ゼロ」が出現したのである。それは核ではなく、2機の旅客機によって。
世界貿易ビルの崩壊は、多くのアメリカ人に深刻なトラウマをもたらした。それをテレビで目撃した多くの人は、夜、眠れなくなったという。人生がある日、突然、終焉する事実を突きつけられ、家族の大切さを認識し、結婚するカップルが増えたという話もある。
それから1年、テロ、そして世界貿易センタービルの崩壊は多くのアメリカ人にさまざまな思いを経験させた。そして、1年経ち、再びアメリカ人はその悪夢と直面するときを迎えた。その迎え方によって、アメリカの社会の質が問われることになるだろう。
ニューヨークの式典は、実に素晴らしいショーであった。悲しみという絶好の味付けで、もっとも劇的に作り上げられたショーであった。テレビは遺族の悲しみの顔を大写しする。遠くから行列を鳥瞰する。
大学から3時過ぎにアパートに戻ってきたが、テレビのライブ中継はずっと続いていた。犠牲者の名前を一人ずつ読み上げる。もうこれ以上の感激場面はできないぞとばかり、テロの不当性と犠牲者の悲しみを強調する。夕方、式典で一人の黒人女性の歌手が歌を歌い始めた。「America the Beautiful」と題する歌は、アメリカを礼賛する歌であった。愛国心を最高に盛り上げるにふさわしい、感動的な歌であった。それに続いて、テレビのニュース番組は、キャピトル・ヒルと呼ばれる米議会の階段に勢ぞろいした議員たちが、「星条旗よ、永遠なれ」の大合唱を行っている場面を写しだした。歌い終わった議員の何名かは星条旗を掲げ、その顔は笑顔に溢れていた。愛国心の高揚に、これほど有効な機会はないといわんばかりであった。
その日の昼、パウエル国務長官は、国連の安全保障委員会で演説をしていた。「テロはアメリカに対する攻撃ではない、それは文明社会に対する攻撃である」と。あくまでも拡張たかい演説であった。チェーニー副大統領が強硬にイラク攻撃を主張しているのに対して、パウエル国務長官は、慎重論を説いた。イラクに言及する言葉はまったくなかった。ニュースの解説者によると、それは翌日の12日に国連総会で演説するブッシュ大統領に取ってあるのだという。
式典に先立ち、ホワイト・ハウスである議論がされた。ブッシュ大統領がどこで演説するかという議論である。最初はマンハッタン島を見渡せるガバナー島で行う案が有力であった。しかし、最終的にエリス島で行われることになった。その理由は簡単である。エリス島で演説すると、背景に自由の女神が入るからだという。政治にとって、この式典もショーでしかないのである。
アメリカ政府が主催する追悼式は、すべて愛国心を高揚させるように、極めて優れた演出がされていた。こうした愛国心の盛り上がりを背景に、おそらくブッシュ大統領はイラク攻撃の挙にでるのだろう。ワシントン大学のキャンパスにあるグラハム教会で11日の昼間開かれた講演で、ピューリッツア賞を受賞した「ボストン・グローブ」紙のケネス・クーパー記者は、講演後の質疑応答で、ブッシュ大統領がイラクを攻撃するかどうかを聞かれて「攻撃するほうに賭ける」と答えた。彼は、英語の“bet”と言う言葉を使ったが、辞書の訳でいえば「賭ける」という意味になる。だが、ジャーナリストとして「賭ける」という言葉はやや非見識なので、おそらく彼は「思う」という程度の気持ちで言ったのであろう。しかし、このテレビを通してみる愛国心の高まりをみると、僕もイラク攻撃に「賭けて」みたくなる。
アメリカは自らを殉教者にすることによって、「大義」を得たのである。本来、自らを「殉教者」にすることによって、反権力の「大義」を手に入れようとしたビン・ラディンは、文明の破壊者として糾弾され、命脈を断たれようとしている。そして、アメリカは「殉教者」として振舞うことで、強引に世界を自分のものにしてしまったのである。
しかし、これがアメリカのすべてでないことを、ワシントン大学のクアド広場の追悼式は教えてくれた。その追悼式の1時間半の間、1度も「アメリカ」という言葉は出てこなかった。「テロを攻撃」言葉すら出てこなかった。静かな追悼式であった。静かというよりは、沈黙の追悼式であった。アラブの学生、パキスタンの学生は、神を敬い、平和を愛するイスラムの賛美歌を歌った。キリスト教のチャプレンは、宗教、人種、性別、国籍を超えた融和を訴えた。そして、題名は知らないが、「沈黙」歌った詩は、人々が一人ではなく、沈黙の中に生まれつつある可能性を歌いあげた。
火のついた蝋燭を掲げ、周囲を見回した学生たちは、「you are not alone」という言葉を暗闇の中に聞いたのである。
この投稿には、まだコメントが付いていません
このコメントのRSS
この投稿へのトラックバック URI
http://www.redcruise.com/nakaoka/wp-trackback.php?p=44
現在、コメントフォームは閉鎖中です。