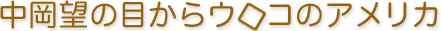私の書評:中西輝政著『アメリカ外交の魂』(集英社刊)ー『諸君!』4月号に掲載
以前、アメリカに関する本の執筆を考えていたとき、書籍の編集者から「アメリカ関係の本はなかなか売れない」といわれ、すこしがっかりしたことを覚えています。随分前のことですが、最近は少し事情が違ってきたのかもしれません。書籍の広告などを見ていると、国際的な問題に関しては、アメリカ関連の書籍が他を圧倒している感じがします。イラク戦争や大統領選挙という大きな出来事があり、また思想的にも保守主義の影響力の増大という現象が見られるからかもしれません。私も昨年の4月に中央公論新社から『アメリカ保守革命』を出版しました。新しい角度からアメリカの政治、経済、社会を分析に寄与できたと自負しています。このブログに掲載する中西輝政著『アメリカ外交の魂』書評は私が『諸君!』4月号に寄稿してものです。玉石混交のアメリカ関係の本のなかで、大きな歴史的視野からアメリカ外交を理解する上で参考になると思い、転載することにしました。なお、蛇足ですが、学生の専攻の傾向から見ると、少し残念ですが、彼らの関心はアジアに向いていて、アメリカ研究はあまり人気のあるコースではなくなっているようです。しかし、アメリカは良い意味にせよ、悪い意味にせよ、日本にとっても学ぶべきことが多くある国だと思っています。そのためにも、もっと良い本がたくさん出るようになることを願っています。私もこれからも知的に挑発的な本を書いて行きたいと思っています。
日米間の人、物、情報の交流は膨大な量に達しているにもかかわらず、日米がお互いを十分に理解しあえない状況が続いているのは不思議である。その思いは私だけのものではなく、本書の筆者にも共通な思いとしてあるようだ。筆者は「あとがき」で「物質主義的な歴史観は、とりわけアメリカを見るとき深刻な誤りに陥らせる。日本のアメリカ観も、やはりこの百年、そうした偏向によって大きく歪み続けてきたところがある。アメリカ文明における宗教のもつ意義が、とりわけ『国家としてのアメリカ』が外の世界に関わるとき、過度に見過ごされてきた嫌いがある」と書いている。
その結果、日本人はアメリカをベーコン流の「物質功利主義」とホッブス流の自己保存のための「力の理論」の二点でしか理解しようとしてこなかったのである。さらに筆者は、こうしたアメリカ観が「今日においても日本の知識人や大衆の中に深く根を降ろしている」という。
こうした日本人のアメリカ観を正すためには「もう一度アメリカを突き放し、その歴史の実相を虚心に見てゆくことしか方法はない」。要するにもう一度アメリカの建国の理念からアメリカを理解しなおす以外に日本人の持つアメリカ観の歪みを正すことはできないという思いが、本書の基調をなしている。それは「国とか文明あるいは長期的にみたときの一つの社会というものは、その始まり、誕生という源に本質があり、その国がどういう誕生の過程を経て出来上がったのかということが、ふつう考えられているよりも重要な意味をもつことがある」という指摘の中にも端的に現れている。「始まりにその本質を見よう」とする分析姿勢が、本書に単なる解説書を越える奥行きと深みを与えている。
本書は「二十世紀アメリカの外交の奇跡―理想と幻想の系譜」と「アメリカ外交を洞察する視座」の二部立てになっている。このタイトルから分かるように、本書は基本的にアメリカの外交政策をアメリカの歴史や文化の視点から分析したものである。筆者は既に『大英帝国衰亡史』と『帝国としての中国』を上梓しており、本書は「帝国史論」三部作の最後をなすものである。
本書は、アメリカの外交政策の思想的、文化的、歴史的な背景を明らかにすることで二一世紀のアメリカ外交の行方を予想しようとする。その分析の中心にアメリカの伝統的な孤立主義思想「モンロー主義」を置き、アメリカ外交が「孤立主義」あるいは「一国主義」と「理想主義」に間で揺れ動いてきた様を活写している。
「始まりにその本質」があるようにアメリカ外交は「ジョージ・ワシントンの呪縛」の桎梏との戦いの歴史であった。
ワシントンは「政治的に外の世界に関わることがアメリカの自由を傷つけ、腐敗させる。軍事力、同盟、そして外交や対外戦略というものは不断にアメリカのモラルと自由を侵食する危険性を持つ」と、アメリカの外交に道徳的な枠組みを与えたのである。それは建国間もないアメリカにとって国際社会で自らが生き残る戦略でもあったが、同時に外交政策を展開するときアメリカに「膨張する力はやむことのない『道徳的問いかけ』と手をたずさえて歩まなければならない運命」を背負わせることになったのである。
外交政策に国民を納得されるための「高度な道徳性」が必要となのである。ブッシュ大統領(父親)が冷戦後の「新しい秩序」を訴えたとき「アメリカは高い倫理的目標を持つことなくして国家たりえない」と語っているのも、こうしたアメリカ外交の持つ宿命を表現したものであった。「ワシントンの呪縛」は、やがて「モンロー主義」へと衣を換えていく。
アメリカの場合、外交政策は憲法解釈の仕方によって規定される。憲法を国内のみで通用するものと考える立場から「孤立主義」が出てくる。憲法の理念は国内のみに適用し、対外的には「普通の帝国主義」を実現するという発想から「膨張主義」が出てくる。そして、歴史の呼びかけに応えることがアメリカの使命だとする立場から「世界の紛争の調停者」としての「理想主義」が登場する。言い換えれば、アメリカの外交政策の課題は常に憲法の制約とどう折り合いをつけるかにあった。すなわち独立宣言や憲法で謳われた「理念」とホッブス的な世界での「力」の間で揺れ動き、その双方を満足させる「文明史的妥協」を図ることであった。だからこそアメリカが「臆病な中立」を脱却し、二つの世界大戦に参戦するには、国民を納得させる「理念」が必要だったのである。
こうしたアメリカの発想を理解するためには、その誕生を見てみる必要がある。それはアメリカが「宗教国家」であるという事実である。アメリカは「厭世感、脅迫観念、ある種の深い悲観論をどこかに秘めたピューリタニズムの独特な魂が精神の核になって始まった国」なのである。憲法を作った人々は、政治は必ず腐敗と衰退するという「政治的悲観論」に立っていた。したがって独立の最初からアメリカは「自らの存在証明を手にしなければ永遠に滅びてしまう」という脅迫観念から常に「救済」の証明を求めている国なのである。それが福音的理念をアメリカ外交の中に持ち込む下地となったのである。
こうした文脈の中からアメリカ外交を眺めてみると、それは「介入→幻滅→理想主義→介入→幻想というプロセスが延々と繰り返し」であった。そして、常に幻滅の後に孤立主義が待っていた。とすれば、これからのアメリカは「テロとの戦いを唱えつつ、やがてもう一度、そのサイクルに戻ってくると考えるべきである」「アメリカは今後、自らの力の低下を自覚するようになったとき、多国間主義に向かうより孤立主義へと回帰するだろう」と、筆者は大胆な予想を下している。
本書の論理的な枠組みは広く、知的な刺激に富む議論が展開されており、紙幅の限られた本欄で十分に紹介しきれないのが残念である。ただ、多くの読者が期待している現代的な問題、すなわちアメリカの保守化、ネオコンの思想、キリスト教原理主義者の台頭、イラク戦争といったテーマの分析がほとんどないためやや迫力に欠けることは否めない。イラク戦争を巡る米欧の対立を「西部の荒野に始まる『西へのベクトル』の行きついた先で初めて『他者としてのヨーロッパ』にであったことが契機」であるというのは美しい表現だが、ロバート・ケーガンが指摘しているように両者の間にある国際社会の理解が基本的に違う観点からも明確に分析すべきだろう。また、アメリカ国内のリベラル対保守主義の座標軸から外交政策を分析すると、また違った視点がでてくるだろう。
以上が『諸君!』に掲載した書評の最初の原稿です。字数の関係で、実際に掲載されたものは、これよりも少し短くなっています。追記としては、2つのことを感じています。1つは、アメリカ外交の展開という点から、現在の状況は特異な状況にあると思われます。それを従来のような「モンロー主義」的な枠組みで理解するのは難しいかなということです。本書は、建国以来のアメリカの精神性を問いながら、外交の意味を分析しているので、こうした直近の問題に対する切込みが弱いのも仕方がないのかもしれませんが。もう1つは、最近、流行の「アメリカ帝国主義論」に対する言及がないのも物足りないという感じがします。とはいえ、筆者の立場は明確で、読み物としても面白い本であると思います。私の『アメリカ保守革命』とあわせて、本書を読むと、面白いアメリカの姿が浮かびあがってくると思います。
この投稿には、まだコメントが付いていません
このコメントのRSS
この投稿へのトラックバック URI
http://www.redcruise.com/nakaoka/wp-trackback.php?p=97
現在、コメントフォームは閉鎖中です。