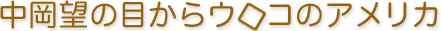金融危機でアメリカ人の生活はどう変わったか:消えたアメリカン・ドリーム
アメリカの景気は急速に回復に向かっています。ただ経済の数字ほど、回復は堅調ではなく、政府の刺激策がなければ景気の”二番底”がありうるとの見方も依然としてあります。しかも景気は回復に向かっているとはいえ、失業率は10%台に留まっています。2010年中は10%台の失業率は続くと予想されている。深刻な不況の影響はまだ色濃く残っており、厳しさには変わりはありません。今回は金融危機後、アメリカ人の生活や生活意識がどう変わったかに焦点を当てました。この記事は昨年の『中央公論』11月号に寄稿したものです。アメリカ社会の変化を描写したつもりです。
日本社会とアメリカ社会はシンクロナイズしながら動いている。あるときはアメリカ社会が先行し、日本が追いかける。別の時は逆に日本が先行する場合もある。二つの社会は極めて奇妙な位置関係にあると言える。今、アメリカで起こっていることは、将来の日本の姿かもしれない。今、アメリカ社会で何が起こっているのか分析した。
21世紀に入ってアメリカは二度、大きく変わった。最初は2001年9月11日の連続テロ事件で世界貿易センターの崩壊を目撃した時であり、二度目は2008年9月15日のリーマン・ブラザーズ証券の破綻と、それに続く深刻な不況に直撃された時である。この二つの出来事は、アメリカの社会的、経済的な構造だけでなく、人々の心理までも大きく変えてしまった。
アメリカの歴史上、アメリカ本土が戦場になったことはなかった。多くのアメリカ人にとってアメリカは最も安全な場所であった。しかし、スローモーションのように崩れ落ちる高層ビルを目の当たりに見たアメリカ人の多くは、聖書のヨハネの黙示録に書かれた“アルマゲドン”が始まったと本気で考えた。その後、フロリダを襲ったハリケーンは、その思いをいっそう強くさせた。また、連続テロ事件は常軌を逸したと言っても過言でないほどアメリカ人を“テロとの戦い”に駆り立てた。それがアメリカの国際的な威信を傷つけ、また国民の自信をも失わせた。
リーマン・ブラザーズ証券の破綻は金融危機に火を付け、1930年代の大恐慌以来という不況を招いた。アメリカの資本主義は大きく傷つき、再びアメリカ人の自信を喪失させることとなった。また10%を超えるのは時間の問題となっている失業の増大は人々の生活だけでなく、人生観そのものも変えつつある。アメリカ経済の成長は個人消費に支えられてきた。多くのアメリカ人は住宅を担保に多額の借金をしながら、ひたすら消費をしてきた。しかし、地価と株価の暴落が家計を直撃し、家計部門の純資産額は208年末から2009年第1四半期までのわずか3ヶ月の間に1.3兆㌦も減少してしまった。その結果、アメリカ人は消費を減らし、貯蓄を殖やし始めた。
この大不況は単にアメリカ人の経済行動に影響を与えただけではない。ニューヨークに本社があるメトロポリタン生命保険会社は、毎年『アメリカン・ドリームの研究』と題する調査結果を発表している。今年の3月に発表された報告は、「金融危機がアメリカン・ドリームにどのような影響を与えたか」について調査が行われている。同報告は「アメリカはアメリカン・ドリームに対して永続的な影響を及ぼす可能性のある非常に大きな変化を経験した」と報告している。
同調査は、一般のアメリカ人がいかに将来対して強い不安を抱いているかを明かにしている。回答者の59%が個人破産に追い込まれることを心配し、64%が住宅を手放さなければならなくなるのではないかと答えている。失業すれば、二週間で蓄えがなくなると解答した人は28%に達している。さらに56%が、来年、失業するかもしれないと答えている。そこには楽観的なアメリカ人のイメージはまったくない。
経済的な苦境を乗り切るために多くの人はライフスタイルも変えつつある。44%の人が、不況によって生活の優先順位を変えざるを得なくなったと答えている。大多数の人は外食を減らして自宅での食事の回数を増やし、旅行は贅沢だと考えるようになっている。40%の人が、買い物は大型安売り店でするようになったと答えている。66%の人は株価や住宅価格の動向に以前ほど注意を払わず、現在は家族や友人、子供、結婚といった“個人的な事柄”を重視するようになっていると答えている。さらに同報告は「雇用不安が高まる中で職場がアメリカン・ドリームの礎石となっており、従業員福利が重要な意味を持ち始めている」「アメリカン・ドリームはこの一年で大きく変わったのは明かだ。人々は人生の成功とは何か考え直し始めている」という興味深い指摘をしている。
どこの国でも不況期には人々は生活防衛的になるものである。しかし、同調査では、こうしたライフスタイルや人生観の変化は一時的なものではないと結論付けている。再びブームが到来すれば、人々の生活スタイルや人生観もまた変わるかもしれない。しかし、同調査が示唆しているのは、今回の金融危機がアメリカ人に与えた影響は日本から見ている以上に大きかったということであろう。
リーマンの社員はどこへ行ったのか
ウォール街はアメリカ資本主義の強さの象徴であった。優秀な若者に一攫千金の機会を与える場所でもあった。短期間で信じられないほどの巨額の報酬を得る可能性を秘めた場所であった。しかし、金融危機の中でベアズターンズ証券、リーマン・ブラザーズ証券、メリルリンチ証券といった名門の投資銀行は姿を消し、ウォール街の様相は一変してしまった。
「ニューヨーク・タイムズ」(9月13日)は「リーマンの遺体安置所の物語」と題する記事を掲載し、元リーマン・ブラザーズ証券の社員たちの現状を報告している。トム・オルクイストは昨年の9月9日に突然解雇を言い渡された。リーマン・ブラザーズ証券が破産法第11条の適用を申請したのは、彼が解雇された一週間後の9月15日である。彼は、その日のことを昨日のように思い出すという。彼は、職を失い、貯蓄をなくしただけでなく、お金を儲けたら、50歳で早期退職をして高校のバスケットボール部の監督になる夢も断念しなければならなかった。かつては投資家相手に住宅証券を売っていたが、今は誰も聞いたことのない証券を売り歩いているという。
元管理職のポストにいたジェフ・シェーファーはフロリダでガソリンスタンドを経営している。レスリー・ゲルバーは1年経ってもまだ失業中で、ストレスにさいなまれている。中にはケン・リントンのようにブームの時に十分に蓄えを作り、現在はジェット機を乗り回している幸運な人物もいる。
リーマン・ブラザーズ証券は、ある意味で日本的な企業であった。社員は仕事が終わったら一緒に飲みに出かけ、一緒に運動をしたり、休暇を取ったり、常に連絡を取り合っていた。しかし、「現在は皆ばらばらになり、まだ金融界への思いを断ち切れない人もいる」と、同紙は書いている。だが、シェーファーは「あまりにも一生懸命、会社のために働いたことに怒りを覚えている。稼いだお金は全てなくなった。いつも出張していて、家族と一緒の時間はなかった。もう一度金融界に戻って、やり直すことはできない」と、今の心情を吐露している。こうした個人の物語は、企業が倒産した時にいつも語られるものである。
金融危機後、ウォール街の雇用数は44万3000名減っている。
だが、政府の救済支援を受け、ウォール街は急速に回復しつつある。生き残った企業は、もはや倒産の悪夢にうなされることはない。地方の小銀行の倒産は続いているが、ウォール街の巨大金融機関はさらに巨大になって寡占状況を作り出している。ゴールドマン・サックスやJPモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカは軒並み史上最高の利益を計上するまでになっている。ゴールドマン・サックスの今年の第2四半期の利益は同社の140年の歴史で最高であった。その最大の理由は、競争企業の相次ぐ倒産で市場が寡占状態になったからである。金融危機は、皮肉にも、生き残った大手金融機関を“焼け太り”させることになったといえる。
役員や社員の報酬は既に危機以前の水準に戻り、3万人の社員を擁するゴールドマン・サックスの場合、社員の平均給与は70万㌦に達している。ロンドンの金融アナリストは、欧米の主要八銀行は2011年に合計14万人強の従業員に対して総額770億㌦の給与を支払うと予想している。一人当たり54万㌦を超える額である。
リーマン・ブラザーズ証券やメリルリンチ証券の破綻を目の当たりにした金融機関は、リスクの高い商品から手を引き、レバレッジ(借入)を減らし、損失に備えて積立金を積み立てている。ゴールドマン・サックスのレバレッジは危機前が24倍であったのが、現在は14倍にまで低下している。アメリカの金融機関はブーム時の狂乱から、正常な状況に戻りつつある。
だが金融機関に対する不信感が払拭されたわけではない。役員に対する高額のボーナスは国民の怒りを買っている。現在、FRB(連邦準備制度理事会)は、金融機関の役員が過剰なリスクを取る事態を回避するために報酬制度を承認制にする規制の導入を検討している。また、昨年、導入された金融機関救済法の中にも政府の支援を受けた金融機関の役員の報酬規制が盛り込まれている。欧州各国政府も報酬を国際的なルールで規制することを主張している。今後も様々な局面で金融機関や金融市場の規制強化が行われると予想され、バブル時のような金融資本主義の暴走にブレーキがかかることになるだろう。
疲弊するメイン・ストリートと地方経済
金融業界を“ウォール・ストリート”というのに対して製造業などの産業や地方経済のことを“メイン・ストリート”という。現在、ウォール・ストリートは急速に回復しているが、メイン・ストリートや地方経済の低迷の色はさらに濃くなっている。アメリカ経済の製造業の長期的衰退はもはや避けがたい状況となっている。
自動車都市デトロイトでは、自動車産業の衰退で都市そのものも機能しなくなっている。工場労働者だけでなく、高学歴のホワイトカラーの雇用調整もかつてないスピードで行われている。自動車会社のビッグ・スリーは工場労働者だけでなく、2006年末から今年の6月までに3万人のホワイトカラーを解雇している。かつては最強の労組と言われたUAW(全米自動車労組)も、雇用維持するための戦闘力を失ってしまっている。
その結果、ミシガン州の8月の失業率は15.6%と、全国平均の失業率を大きく上回っている。デトロイトの失業率は17.7%とさらに高い水準になっている。同州の労働者の20%がフルタイムの仕事を探しながらも、パートタイムでしか働けない半失業の状況に置かれている。デトロイトの住宅市場に回復の兆しはなく、7月時点で住宅価格はピークを付けた2006年初と比べて45%下落し、地域社会の荒廃が続いている。同州では、高賃金が期待できる防衛関係や代替エネリギー関係、医療関係の企業の誘致を進めているが、目立った成果は見られない。
職を失った人は悲惨である。あるクライスラーのエンジニアは年収11万㌦を稼いでいたが、早期退職をして現在はパートタイムで働いており、週休はわずか500㌦である。クライスラーの製品開発の責任者であった男性は年収10万㌦以上あったが、早期退職して得た現在の仕事の年収は3万1000㌦である。職を失うことの影響は収入の減少に留まらない。アメリカの健康保険制度は企業が提供しており、仕事を失うことは健康保険をも失うことになる。
企業年金も同様である。アメリカでは企業年金は確定拠出型年金(いわゆる「401(k)」と呼ばれるもの)で、企業は従業員の積立額に見合う金額を拠出する仕組みになっている。しかし、モトローラなど拠出を中止する企業が続出している。さらに同年金の運用対象である株価の下落も加わり、多くの労働者は退職後の生活に不安を覚え始めている。多くの人々は、早期退職をして人生を楽しむという夢を断念せざるをえなくなっている。
アメリカの雇用情勢は数字よりも厳しい。8月の全国平均の失業率は9.6%であった。しかし、7月の州別の失業率を見ると10%を超える州は16州に及び、ミシガン州が最も高く、続いてロードアイランド州の12.9%、ネブラスカ州の12.7%、カリフォルニア州の12.1%と続く。カリフォルニア州のエル・セントロ地域の失業率は30%を上回っている。
現実の雇用情勢は、数字以上に厳しいとみられる。アメリカ経済の成長を支えてきた要因のひとつに、毎年、100万人を超える外人労働者の流入があった。しかし、昨年、初めて外人労働者は流出に転じた。全国の外人労働者の数は9.9万人減少している。外人労働者の多いカリフォルニア州でも、その数は16.5万人と初めて減少に転じている。こうした外人労働の減少がなければ、その地域の失業率はさらに高くなっていただろう。外人労働者が雇用調整のバッファーの役割を果たしているのである。
こうした雇用情勢は地方自治体の財政を直撃した。民間研究機関センター・フォー・バジェット・アンド・ポリシー・プライオリティが六月に発表した報告では、今年度、税収不足で歳入欠陥に直面する州は48州に達すると予想されている。財政赤字を解消するには増税か歳出削減しかないが、住民の増税に対する反対が強く、各州政府は大規模な歳出削減を迫られている。カリフォルニア州では医療費や大学定員の削減、公務員の賃金凍結などが行われている。今後、さらに公共サービスの低下は避けられない状況である。またミシガン州でも2008年の個人所得が前年を下回り、厳しい財政状況に対応するために一般会計で約13億㌦、学校の救護所予算4億1200万㌦の削減などを提案している。
金融危機に直撃された大学
金融危機は大学にも二つの面で重大な影響を与えた。ひとつは大学の財政に対する影響であり、もうひとつは学生に対する影響である。
アメリカの大学は優れた教育内容に加え、安定した財政基盤を持っているのが特徴である。たとえばハーバード大学は巨額の基金を持ち、授業料を無料にしても10年間、運営していけると言われてきた。基金の運用利回りで経費を賄うことができた。基金の過去10年の運用利回りは年率で平均13.8%と極めて高水準であった。しかし、金融危機で投資していた株価や不動産価格が暴落し、大学基金は巨額の損失を計上したのである。同大学の基金の額は、金融危機が始まる前の2008年6月末現在で369億㌦あった。しかし、金融危機に直撃され、同年末までに約80億㌦の損失を被った。最終的に約30%の損失となったが、これは1974年に計上した過去最高の損失約12%を大幅に上回るものであった。基金の運用益は大学の経費35億㌦の約35%を占めているだけに、この損失計上は大学の経営基盤を揺さぶるものであった。
他の大学基金も同様な損失を被っている。ハーバード大学は経費節減や基金の財産の取り崩し、スタッフの採用や給与凍結などで対処する方針を発表しているが、他のエリート大学であるブラウン大学やコーネル大学なども経費節減や採用凍結を行うことを明かにしている。だが、金融危機は基金の運用にダメージを与えただけでなく、重要な収入源である寄付金にも暗い影を投げかけている。寄付をする富裕層も金融危機で資産が目減りをしており、今まで通りの寄付を期待できなくなっているからだ。
事態は2009年に入っても基金の運用は好転せず、ハーバード大学基金はさらに30%程度の損失が予想され、同大学は6月23日に職員二七五名をレイオフすると発表した。さらに経費削減として休日の大学のシャトルバスの運用を中止し、大学寮の朝食は暖かい食事を提供するのを止め、さらに博士課程の学生の採用を減らすという対策を講じている。職員のレイオフは他の大学でも見られ、ミシガン州立大学も600名の職員の削減を発表している。
金融危機は学生にも影響を与えている。アメリカの大学生は親に授業料を頼ることは少なく、大学の奨学金か借入で資金を得ている。四年生の私立大学に通う学生の場合、借入額の中央値は2万2375㌦となっている。これは4年前の2万1238㌦より5%増えている。ただ、この借入の中には両親や親類、友人などからの借入やクレジット・カードを使っての借入分は含まれていない。調査を行ったカレッジ・ボードのスタッフのサンディ・バウムは「私立大学の学生は借入がますます難しくなっている。学生に融資をしていた銀行の数も大幅に減っている」と、今後の借入はさらに厳しくなると予想している。
不況の中でも授業料は上昇している。高い授業料を払って学位を取る価値はあるのだろうか。ある調査によれば、大卒の年収の中央値は高卒よりも74%も高いという結果がでている。アメリカ社会は学歴社会で、学位がないと良い仕事に就けないのが現状である。学士号では管理者になれず、修士号や博士号を持っていることが昇進の条件になっている。その意味では、教育投資の効果は十分期待できるといえよう。言い換えれば、学歴の有無が所得格差の大きな源泉になっているのである。
ただ金融危機以降、学生の意識に変化が現れている。「ウォール・ストリート・ジャーナル」(9月18日)は「金持ちの勢いがなくなったように金融も魅力が失せた」と題する記事を掲載している。22歳で工学部の学生は一年前には金融業界に就職することを望んでいたが、現在、その気はまったくないという。その学生は「金融危機が起こらなかったら間違いなく金融業界に就職していただろう。金融業界以外ではあまりお金は稼げないだろうが、夜は帰宅でき、自分のやっていることに満足感を覚えるだろう。それはお金を稼ぐよりも価値あることだ」と語っている。
同記事は「金融バブルは弾け、何十万いう従業員が解雇され、大学の新卒者は別の産業で仕事を求めている」と書いている。産業構造的にも金融業界は大きな成長が見込めないとの分析もある。大統領経済諮問委員会が7月に発表した報告では、金融保険業界で働く人の割合は2008年末の4.8%から2016年には4.1%にまで低下すると予想し、「金融サービス部門は不況前の水準から大幅に低下する」と指摘している。就業者数が増えると予想されているのは、医療・教育サービスの分野である。
これはハーバード大学の卒業生の就職先の変化でも裏付けられている。2009年の卒業生で金融業界に就職した比率は20%に過ぎなかった。金融危機が始まる前の2008年の卒業生の47%が金融業界に就職したのと比べると、大幅な減少である。ここでも教育業界や医療業界に就職した学生の数は倍増している。
深刻化する貧困と医療保険の問題
アメリカ社会の最も深刻な問題は、貧困の問題である。最も豊かな国のひとつでありながら、貧富の格差は発展途上国なみである。そうした状況に金融危機に始まる不況が直撃した。国勢調査局が発表した「2008年の所得と貧困、医療保険報告」によると、貧困率は2007年の12.5%から13.2%へと上昇している。貧困線(一人暮らしで年収が1万0830㌦、四人家族で2万2050㌦)以下で生活している数は3980万人と、前年に比べて260万人増加している。このいずれの統計も2008年のもので、不況がさらに深刻化した2009年にはさらに増えると予想される。
また、2008年の家計の実質所得の中央値も前年比で3.6%減少し、5万0303となっている。3年連続で増加した後の減少であり、ここでも不況が影を落としている。貧困層や所得の減少が見られる地域は、住宅バブル破裂の影響が大きかったラスベガスなどのサンベルト地帯と、自動車産業など製造業への依存度が大きかったデトロイトなどの地域である。
最貧層と最富裕層の所得格差は若干拡大している。所得五分位の最富裕層の国民の総所得に占める比率は、2007の49.7%に対して2008は50%と若干増えている。他方、最貧困層の比率は3.4%と横ばいに留まっている。ちなみに富裕層の上位5%の占める比率も21.2%から21.5%へとわずかながら上昇している。いずれにせよ、富裕層と貧困層の所得格差は絶望的ともいえるほど開いていることに変わりはない。
さらに物価上昇分を調整した実質ベースでみると、2008年の労働者の賃金は1983年とほぼ同じである。この25年間、実質賃金がまったく上昇していないというのは驚きである。さらに追い打ちを掛けるように、低所得者向けのサブプライムローン問題が表面化し、労働者の多くは家を失っている。所得の伸び悩みに加え医療費と教育費の増大のなかで低中所得層が生き延びることができたのは、低金利による借入が可能であったからだ。クレジット・カードによる借入が急増しているのも、その証左である。一般の国民が金融機関の高額ボーナスに怒りを覚えるのは当然といえよう。
ただ、資産格差はやや違った様相が見られる。住宅価格と株価下落は富裕層により大きな打撃を与えた。ボストン・コンサルティング・グループの調査では、500万㌦以上の資産を運用している層の資産は2007年の22.6兆㌦から2008年には17.7兆㌦に減っている。低所得層も住宅価格の下落で資産の目減りは見られるが、全体として資産格差はわずかながら縮小していると推測される。しかし、元々、資産家と労働者の資産を比較すること自体が無意味なほど、格差は拡大しているのである。
さらに、アメリカが解決しなければならない深刻な問題がある。それは医療保険制度の改革である。オバマ政権は政策の最優先課題として国民皆保険制度の設立を図ろうとしている。ただ日本では想像もできないほど国民の抵抗は強い。
国勢局の調査では、2008年の無保険者の数は4630万人、人口比では15.4%に達している。前年比で60万人増加している。アメリカでは医療保険は民間の保険会社に加入するか、企業が提供する保険に加入するのが一般的である。問題は失業すると企業の医療保険を使えなくなることだ。失業による所得喪失に加え、過大な医療保険費の負担がのしかかることになる。日本のような国民皆保険制度がないため、不況になると大量の無保険者が生み出されることになる。
所得が低ければ「メディケイド」と呼ばれる政府の低所得者向け医療制度の対象になり、高齢者は「メディケア」と呼ばれる政府の高齢者医療制度を利用できるようになる。問題は、メディケイドが利用できない年収が3万ドルから4万㌦の層である。その所得層が無保険に陥る可能性が最も高い。所得減少でメディケアの対象となった数は、2007年の3960万人から2008年には426万人と14%以上も増えている。これも不況の影響といえよう。メディケイドの対象者数は、430万人で、前年比14.3%増加している。退職後にも潤沢な医療保険を提供していたGMは、再建に際して、退職者がメディケアの対象になる年齢に達したら、健康保険の対象から外すと通告している。高齢化が進めば、対象者数はさらに増えるだろう。
オバマ政権の皆保険制度導入は厳しい抵抗にあっている。多くのアメリカ人は、医療保険は自己責任であると考え、皆保険制度が導入されれば増税になると心配しているのである。最近のオバマ大統領の支持率の低下の要因は、医療保険制度改革に原因があるのは間違いない。
アメリカの若者にとっても将来は明るくない。労働組合のナショナル・センターであるAFL-CIO(米労働総同盟産別会議)が九月に「若い労働者-失われた10年」と題する報告書を発表した。同報告によれば、35歳以下の労働者の34%が十分な所得がないために家族と同居しており、10年前と比べるとはるかに大きな雇用不安を感じており、医療保険に加入するのも無理だと答えている。25%の若い労働者は毎月の支払いをするだけの収入がないと答え、半分以上が未来に希望を感じられないと答えている。この10年間に若年労働者の状況は極めて悪化しており、リチャード・ツルムカAFL-CIO会長は「この10年間で若者の機会が失われ、彼らは生きていくのに精一杯である。結婚を断念し、子供を産むのを先延ばしし、いつまでも大人になれない状況が続いている」と説明している。
31歳の若い労働者ネイト・シェーラーは「結婚して両親の家に引っ越した。月々の収入でなんとか生活はできるが、借金は返せない。子供が欲しいが、経済的に無理だ」と、生活の現状を語っている。アメリカの若者は独立心が強く、早く自立するというのが一般的な印象であった。しかし、この10年の経済情勢の変化で、日本とは違った意味で多くの若者がパラサイト化し、ワーキング・プア化しているのである。
コラムニストのボブ・ハーバートが「ニューヨーク・タイムズ」(8月11日)に「恐るべき現実」と題するコラムを寄稿している。その中で同氏は「アメリカの若者、特に若い男性の窮状は恐るべき状況である。実際に働いている割合は61年で最低である」、「これはアメリカの最大の問題であり、最優先されるべき問題である」と書いている。
若者が将来に希望が持てない社会という点では、日米共通しているのかもしれない。
この投稿には、まだコメントが付いていません »
このコメントのRSS
この投稿へのトラックバック URI
http://www.redcruise.com/nakaoka/wp-trackback.php?p=314